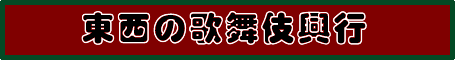
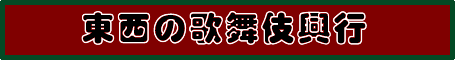
![]()
![]() 終戦後、関西での歌舞伎興行が極端に少なくなった時期がありました。 最近は松竹座の開場など、戦前とは比較にならないまでも歌舞伎の隆盛はおめでたい限りです。
終戦後、関西での歌舞伎興行が極端に少なくなった時期がありました。 最近は松竹座の開場など、戦前とは比較にならないまでも歌舞伎の隆盛はおめでたい限りです。
そこで、関西における歌舞伎・文楽の興行実態はどのようであったのかを調べたものです。その後、さらに東京における同様の調査を加えました。
![]()
![]() 関西では歌舞伎については松竹が独占していたようなので、松竹の資料で殆ど全貌が見えるように思われます。然し、東京は昔からの興行主がたくさんいて、松竹以外にも歌舞伎を自主興行したようで、松竹の資料だけでは十分ではないように思われます。特に、東京における文楽の興行が少なすぎるようです。 国立劇場は大変詳しく、特に各興行の入場者数を公表しています。
関西では歌舞伎については松竹が独占していたようなので、松竹の資料で殆ど全貌が見えるように思われます。然し、東京は昔からの興行主がたくさんいて、松竹以外にも歌舞伎を自主興行したようで、松竹の資料だけでは十分ではないように思われます。特に、東京における文楽の興行が少なすぎるようです。 国立劇場は大変詳しく、特に各興行の入場者数を公表しています。
![]()
![]() 取り上げた歌舞伎の定義は明確ではありません。歌舞伎らしい題名の狂言を、歌舞伎らしい名前を持った役者が出演している興行を行っている劇場(小屋)とその時期を、個人的な興味と関心と気分で取り上げ、並べ替えたものです。
取り上げた歌舞伎の定義は明確ではありません。歌舞伎らしい題名の狂言を、歌舞伎らしい名前を持った役者が出演している興行を行っている劇場(小屋)とその時期を、個人的な興味と関心と気分で取り上げ、並べ替えたものです。
従って前進座はそのときの演目によっています。市川少女歌舞伎は取り上げておきました。また、若手の歌舞伎は含まれています。ただし、これ以外にも前進座が他の劇場で歌舞伎狂言(助六など)を演じていますが、資料が手元にありません。さらには、公文協などの巡回興行もありますが、含まれてはいません。中村錦之助や大川橋蔵も含まれません。スーパー歌舞伎も除きました。
松竹100年史をベースにしているため、各劇場の自主興行の場合は記録がありません。
さらに終戦直前は新派と歌舞伎が度々合同上演しています。これらは適当に選択しています。
![]()
![]() 興行期間は10日前後をめどに短期興行としています。1ヶ月に短期興行が2度あるときは合計日数でみています。1興行が2ヶ月にまたがるときは気分でそれぞれのつきに分割したときと片方に入れている場合とあります。
興行期間は10日前後をめどに短期興行としています。1ヶ月に短期興行が2度あるときは合計日数でみています。1興行が2ヶ月にまたがるときは気分でそれぞれのつきに分割したときと片方に入れている場合とあります。
![]() 殆どが気分で整理していますのであしからず。
殆どが気分で整理していますのであしからず。
![]() 洩れているものを気づかれたらお教え下さい。
洩れているものを気づかれたらお教え下さい。
![]()
【参照資料】各月番付、演劇界(各月号)、「昭和の南座 資料編上中下」松竹発行(中川芳三編)、
「松竹100年史 資料編」、国立劇場30年の公演記録、三越劇場事務所資料、
日生劇場30年史、その他
