|
===お客に通じた“意気込み”=== “成駒屋父子”お江戸大当たり土産話
「鴈治郎」 八月の演舞場は自分でも本当に面食うてしまうほどでした、まぐれ当りというと語弊があるかも知れませんけど、我々上京組の意気込みというものが東京のみなさんに通じたらしいことは事実です、それに評判をいただきました「曽根崎心中」は宇野信夫先生が近松の味わいを生かして、しかも近代的にアレンジして下さいましたので、大変よかつたのではないでしょうか、浄るりも使いますし、セリフも義太夫口調で、何か新しいところもおました [扇雀] 本文を生かして、ほとんど原作通り最後の心中場まで演りましたが、これは大阪でも珍らしいことだそうですね、例の「足のさわり」ではお客が笑うだろうと思っていましたが、反対に受けたようです、これは女形だから出来たことで「女優さんでは出来ない相談だ」という話もききましたが、如何に女形の私でも縁の下にいるお父さんの頭の上で腰かけたまま足を使って「さわり」をするのですから、舞台があくまでどうなることかと心配でしたよ(笑) [鴈治郎] 原作通りの手順でいくと客が舞台につれホッとしたり、心配したり、一緒に芝居の仲にとけ込んでくれるのです、さすがは近松です、宇野先生がそれをまた巧く生かして下さいましたから・・・とにかく、今の処ではどんなにほめていただいても私らの芸は上つ面だけをコンクリートで固めたようなもので、底の方まで全部しっかり固めんと話になりません [扇雀] 父子で〝イロ″をしているのに全然不自然な感じがないとほめて下さつたそうですが、本当に演っている間は役者同士で、余り親子など思いませんね [鴈治郎] 「曽根崎心中」は結局お初の芝居で、あんたはもうけ役やった、私は縁の下に入つて頭の上で芝居せられたり(笑) [扇雀] それだけに、心配でしたし、大仏先生、北条秀司先生、宝塚の人、S.K.Dの人、菊五郎劇団、吉右衛門劇団の先輩がこられるし江利チエミさんは毎日イ席で見ているのです、あらゆる方面の人にテストされてるみたいでお初の顔をこしらえながら知らぬ間に今までになくやせているのでびっくりしました、芸術院の高橋誠一郎先生が前の方でメガネでのぞいていられますしね・・・、話もしたことのない有馬稲子さんが花束に「ご成功お日出とう」と書いて楽屋にとどけて下さつた時もうれしかつたですね |
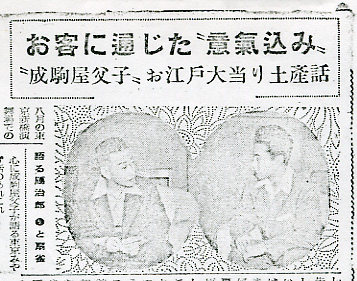 八月の東京新橋演舞場での関西歌舞伎は夏枯れの八月興行としては珍しい大入をつづけたが、東京ファンを沸かせた原因の大半は鴈治郎父子の「曽根崎心中」での好演にあつたといわれ、今更のように上方役者の上方狂言の価値が認められたわけである、以下はこの近松物を中心に成駒屋父子が語る東京みやげ話のあれこれ――
八月の東京新橋演舞場での関西歌舞伎は夏枯れの八月興行としては珍しい大入をつづけたが、東京ファンを沸かせた原因の大半は鴈治郎父子の「曽根崎心中」での好演にあつたといわれ、今更のように上方役者の上方狂言の価値が認められたわけである、以下はこの近松物を中心に成駒屋父子が語る東京みやげ話のあれこれ――