|
====滝沢の好演==== 「セールスマンの死」 −劇評− 一ツ橋講堂の民芸公演
ことに意識の流れのなかで、人物の幅をひろげてゆくあたりは見事で、特筆していい。 ◇・・アーサア・ミラーが現代米国の社会機構を透視して、そこから一人の老セールスマンを取りあげその一家の悲劇と保険金を念頭において自殺してしまう主人公をつくりあげた意味は深く、その背後には作者の強い理想を伺うことができる。 その現代性に裏打ちされたこの作品は、ざらに作劇術の特異な手法に成功した点で高い位置を占める。 ◇・・舞台はウイリイ家の三つの部屋を見せた装置で(伊藤喜朔)照明(穴沢喜美男)の協力をフルに用いて展開される芝居である。六十の坂をこえたウイリイは疲れきって帰宅するが、息子のビフ(宇野重吉は後半がいい)とハッピイ(佐野浅夫)の将来が、かれの頭の中をめぐっている。 妻リンダ(小夜福子も最後の幕切れで好演)のいたわりも、すでに夫ウイリイの自殺を見透しているところに、不気味なサラリーマンの末路を暗示する眼が光っている。しかし、観客はそれを感傷的に受けとつてはならない。 ◇・・二幕だが、正味三時間十分を要する構成である。ウイリイは普通の父親であり、セールスマンであり、庶民的な信念をこしらえあげており、下積みの人間であり、死に直面していて、しかも壮年時代の明るさが舞台の上で蘇えってくるのである。 そういう要素が正確な劇的流れ(回想場面がただの回想にならず)のなかで拡大されてゆき、しまいに巨大な象徴性をもつてくる。息子たちも母親も全く同じ方法でこの芝居をふくらませリアリティを発揮するのである ◇・・ウイリイが会社を首になる辺りから、レストランで子供たちと会食し、口論になる件りは頂点だが、随所に芝居のテコが仕掛けられており、久しぶりで本格的な戯曲にふれた想いがある。 菅原卓の演出もテンポに乱れがなく、まず成功。(お)=写真は滝沢のふんしたウイリイ=廿八日まで |
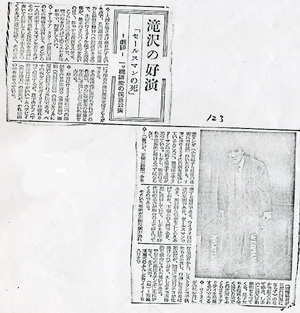 ◇・・人間を描きあげ創りだすという点で、この戯曲は卓抜した構成力と綿密な舞台への配慮があるので、主役のウイリイを演ずる滝沢修が、従来のぎらつく技巧を払いのけて、鮮やかな演技をみせる。
◇・・人間を描きあげ創りだすという点で、この戯曲は卓抜した構成力と綿密な舞台への配慮があるので、主役のウイリイを演ずる滝沢修が、従来のぎらつく技巧を払いのけて、鮮やかな演技をみせる。