0181−1 S24.07.15 大阪新聞? 大阪日日新聞?
(1) 演劇 浮び出た若手 菊五郎亡き後の歌舞伎 期待される昭和歌舞伎
(2) 芸苑余話 [菊五郎一座解散]
|
====演劇 浮び出た若手 菊五郎亡き後の歌舞伎==== 期待される昭和歌舞伎
[今日]の歌舞伎殊に戦後の歌舞伎の魅力は菊五郎の存在が大半を占めていたといっても過言ではあるまい、六代目は父五代目の型も更に洗練し心理的な裏付けをさえして演技に精巧を極めていたのである、それは歌舞伎を現代のものとして次代の俳優に受継がすべきバトンの役目ををも含んでいた明治の歌舞伎攪(繚?)乱期は団、菊、左によって保たれていた、スケールは違うが今日の斯界は往時と一脈の共通性を持っていた、日囗囗囗一角が崩れたのである [残る]吉右衛門は近来、ますます保守的な傾向をとり古典の殿堂に立籠もりつつ若手の補導役を兼ねている、時代物の得意芸は上演できようが、世囗囗囗」等「寺子屋」の源蔵等は、菊あつての吉、吉あつての菊で、今では上演の価値を失った、この点、菊五郎の死は吉右衛門にとっても大きなマイナスである、猿之助の場合は、彼の若さ、新しさが成熟せず煮えこじけたままで現在に至り、団、菊、左時代の左団次の地位から脱却しきれぬとみられる 「■■」若手歌舞伎に課せられ囗囗囗スピードでクローズ・アップされてきた、いうところの若手俳優の主流は、海老蔵、染五郎、松緑、もしほ、芝翫、梅幸、友右衛門等で形成されている、海老蔵、芝翫の伝統的な風格、染五郎、梅幸の堅実さ、松緑、友右衛門の清新さ、もしほの技巧と立役、女形にそれぞれユニークな傾向がみられるのも楽しみである、この人々の特色を活かし、古典に新作に腕を揮うならば溌らつとした舞台が見られよう [然し]現在の松竹の企画は安易にすぎて過去の幻影を追うばかりである、海老蔵には先代羽左、染五郎は吉右衛門、松緑、もしほには世話物や所作物における六代目の面影を求め芝翫にも無理を承知の「ほしい蔵」の淀君を演じさせている、勿論先輩の型を勉強することも必要であるが故名優の面影を若手に偲ぼうとするのは落日の夕映えを讃美し“歌舞伎エレジー”を奏でるだけである、無理を押し切る域に達せぬ若手には迷惑至極で見る方も迷惑となる、まして彼らが第一線に起つ時となったのである自分の身に合わぬ役は拒絶する程の気概がなければその責任は果たせない、そ囗囗囗交流も活発に行われるべきである [既に]寿三郎、鴈治郎、富十郎、我当の東上は実現しているが、互いに腕をみがき合って技芸の向上を計るのもよい、寿三郎の演技は寧ろ東京向きともいえる、菊五郎を歌舞伎最後の人にしてはならぬ、歌舞伎は時代の流れに即して行くのが本来の姿である、菊五郎囗囗囗著に示した一人だった、団、菊、左没後は歌舞伎なきが如くいわれた、しかし歌舞伎は減びなかった今日も同様の時代である、菊五郎の影響が薄らぎこれからの若手は菊五郎歌舞伎を乗り越えた昭和歌舞伎を完成することが第一の務めで、又それが歌舞伎を隆盛に導く一つの途なのである ====芸苑余話==== [菊五郎一座解散] ◇・・盟主菊五郎を失った同一座は今後どうするかについていろいろ考えられているが、結局は一座を解散して松緑、梅幸、男女蔵、彦三郎ら自由の立場で活躍することに当事者の意見が一致した ◇・・また菊五郎の名跡は実子の九朗右衛門がつぐことに大体決って囗囗囗、時期は未定である [光頭活用のチャンス] ◇・・大映京都で撮影中の「幽霊列車」は金語楼、アチャコ、エンタツと笑いのべテランが顔を揃えているだけにスタジオ内はゲラゲラの連発 ◇・・エンタツ、アチャコが熱演最中のある日、停電となって一同暫く手持無沙汰、その時ヤミ中に声あり「ライトの代りにアタシが逆さになってぶら下がろうか?」声の主はいわずとも知れた金語楼 [柳の下の代用品] ◇・・来月の大阪歌舞伎座は大正年間河内に起った十人斬り事件に取材した「河内音頭」が上演されるが、琵琶入り「須磨の仇浪」の大当たりに味をしめて、今度は浪曲入りで入りで客を呼ぼうとの計画 ◇・・「そういつも柳の下にどじょうはいないよ」との演劇フアンの声をきいた寿海が「柳の下へはどじょうの代わりに幽霊を出しますから大丈夫・・」(第二部に寿海初役のお岩で「四谷怪談」がでる) [二十年目のカムバック] ◇・・ニューフェイスが続出するがカムバックも多い映画界、作品の上でも、松竹で菊池国芳の「己が罪」から取材した「母呼ぶ鳥」を製作すれば新演技座では二十数年前、吉川英治の名声を決定的なものにした「鳴門秘帖」を長谷川一夫主演でクランクする
|
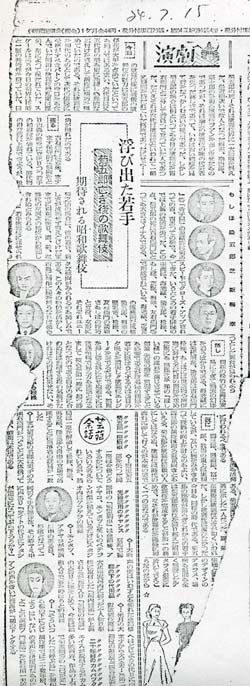 菊五郎の死−それは歌舞伎界に一大衝撃を与えた、最近相次いで故人となった梅玉、幸四郎、宗十郎の訃報ら歌舞伎ファンを悲しませたものであったが、それは過去の歌舞伎の味の代表者を失った淋しさであって、いわば古い錦絵を見て昔をなつかしむ老いの繰言であった、しかし菊五郎の場合は何といつても今日の歌舞伎を吉右衛門と二分して背負って立つていた人であった、たとえそれが六代目歌舞伎といわれて一部に疑問を持たれていた芸統であったにせよ・・・
菊五郎の死−それは歌舞伎界に一大衝撃を与えた、最近相次いで故人となった梅玉、幸四郎、宗十郎の訃報ら歌舞伎ファンを悲しませたものであったが、それは過去の歌舞伎の味の代表者を失った淋しさであって、いわば古い錦絵を見て昔をなつかしむ老いの繰言であった、しかし菊五郎の場合は何といつても今日の歌舞伎を吉右衛門と二分して背負って立つていた人であった、たとえそれが六代目歌舞伎といわれて一部に疑問を持たれていた芸統であったにせよ・・・