|
昼夜の狂言七種、それぞれに趣向もありねらいもわかるが、さてその全部を見終って最後に印象に残ったものが、現代カブキめかせた「新平家物語」でなくして、むしろきわめて古い黙阿弥物の「小猿七之助」だったことは皮肉な興味である。 「新平家物語」はこの前の二編に比べると今度の第三編はかなり見劣りする。保元の乱のようなこみ入った筋立てを説明するにしてはいささか脚色に不備があるようだし、さらに中心人物が清盛(寿海)と崇徳上皇(寿海)と二人に分裂している感じも散漫である。 もちろん、そうした不備や散漫があるにしても、この新しい作品は少くとも時代と人間を書こうとしている。あさましい我欲と我欲がいがみ合うなかに、ひとり水守の麻鳥(鴈治郎)のみが人間愛の真実に生き抜こうとする作意にも、どうやら現代への批判と寓意がよみとれ、それが今日の観客にも十分同感され得るのである。 ところで、この「新平家物語」と対照される黙阿弥の「小猿七之助」は江戸末期の白浪狂言である。黙阿弥は悪の賛美者として知られているのだが、この作品の主人公の小猿七之助にしても洲崎土手の雷鳴にまぎれ奥女中滝川にいどむ。さらにこの男は自分の肉親を救うためには平気で他人の肉親が殺せる男なのである。こうした世紀末的なニヒリズムの肯定と、その英雄化に黙阿弥の世界の不健康さがある。 しかも、それでいて前の「新平家物語」とこの「小猿七之助」とをあわせ観るとき、その芝居の面白さにおいて前者よりもはるかに後者の「小猿七之助」に軍配のあがったところに皮肉がある。 それは要するに「小猿七之助」には歌舞伎の美があったからでないか。歌舞伎の詩がくめたからでないか。黙阿弥のすぐれた作劇術とともに、そこに歌舞伎のよろこびが感じられたからでないか。なるほど「新平家物語」には現代に通ずる批判精神がある。それは如何にも新しいのだが、しかもそれは黙阿弥狂言の豊醇な歌舞伎の魅力にかなわない。この黙阿弥の勝利は歌舞伎の将来にはなはだ示唆的な意味を含む。
以上の二狂言のほかでは珍しい「白縫ものがたり」が出ているが一向に草双紙好みの味でなくてつまらない。しよせん今日の俳優には無理な狂言なのであろうか。近松の「博多小女郎浪枕」では鴈治郎の惣七と扇雀の小女郎とが純粋な上方狂言を楽しませるが、これも上の巻の「元船」の省略がやはりさびしい。 これらの低調さに比べると、綺堂物の「新宿夜話」は元来が東京新宿の宣伝劇でいながら、こんな宣伝劇においてさえ綺堂の着想はさすがに光っている。そして寿三郎の甚五左衛門も芸格に適切で立派だった。(山口広一)=写真は「小猿七之助」の洲崎土手 |

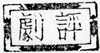 八月一カ月かかって観客席を改装した歌舞伎座はこの九月から新しく再開場している。
八月一カ月かかって観客席を改装した歌舞伎座はこの九月から新しく再開場している。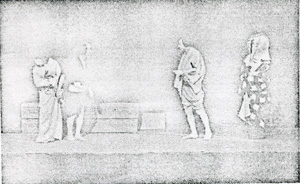 寿海の小猿七之助は後半の「三日月長屋」からあとがさすがにこの人の演技力で優秀である。ただ残念ながら前半、特に肝心の「洲崎土手」では愛きょうがあり過ぎて善人めくのが欠点で冴えない。富十郎の滝川は相も変らず感情の起伏がキッパリしない。その他では仁左衛門のお坊吉三がカットのおかげで損をしているが、三右衛門と雷蔵との勧進坊主、彦人の娘おなみなどよく出来ている。
寿海の小猿七之助は後半の「三日月長屋」からあとがさすがにこの人の演技力で優秀である。ただ残念ながら前半、特に肝心の「洲崎土手」では愛きょうがあり過ぎて善人めくのが欠点で冴えない。富十郎の滝川は相も変らず感情の起伏がキッパリしない。その他では仁左衛門のお坊吉三がカットのおかげで損をしているが、三右衛門と雷蔵との勧進坊主、彦人の娘おなみなどよく出来ている。