|
オルゴールとサキソホンを持った貧しい街の詩人が通行人をつかまえて、それぞれの思い出へ誘い込む。この誘い込み料が金百円也というわけで、その街の詩人は思い出の美しさのみが人間の生きて行く突っかえ棒だと説く。 思い出を持たない花売娘、自分の仕事に情熱を打ち込んでいるチンドン屋、社会批判をやる乞食など次から次へにぎやかに登場する通行人にまじって、夜の女とアメリカ兵とがその思い出を買って行く。そして最後にその夜の女の思い出が現実とのつながりを持ちだして来て、彼女のかつての恋人が殺人を犯した街の顔役として眼の前へ現れて来ることになる。 これは詩情と空想と笑いとの入りまじったロマンチシズムの楽しさである。近藤準のその思い出を売る男のほか、それぞれに演技もそろっていて新人級の成功としたい。 矢代静一の「城館」は難解な芝居である。私はこうした作者の独善的なひとり合点の芝居を採らない。なんとでも解釈できるこんな演劇のアブストラクトは困る。正しくいえば、アブストラクトでなくとも観客にアブストラクトとして受けとられるような芝居が困るのである。 真船豊の「松花江の月」はラジオドラマの舞台化だということだが、なるほどこれは耳で聞く芝居である。月の出た松花江のほとりで二人の若い未亡人が人生について、愛情について、虚偽について、孤独について、いろいろ語り合う。結局はその対話だけの味だがそしてそれがどうという哲学的な内容も持ってないのだが、どこやら炉辺でしみじみと随筆を読むような香気があって、楽しい芝居になった。 その二人の未亡人を荒木道子と賀原夏子とがやる。ともに実力を示した悪くない出来だが、特に荒木の表情に注目したい。というのは、荒木の顔は端麗だが平凡で、意思と表情を持たない顔なのだがそれだけにどんな意思でも表情でも自由に書ける顔である。そしてそれを自由に書くだけの手腕を荒木なら持ち合せている。今後とも荒木道子の可能性の一つがこの顔にかかっているといっては過言だろうか。 話をもとへもどすが、この「松花江の月」では最後のトロイカの場面が無理だ。それは演劇の限界を超えているからである。疾走するトロイカに疾走する人間の感情を託するなどという効果は、やはり映画かラジオでないと駄目だろう。(山口広一)=二月三日まで=大阪毎日会館 =写真は「思い出を売る男」近藤の街の詩人(左)と広沢の街の顔役 |
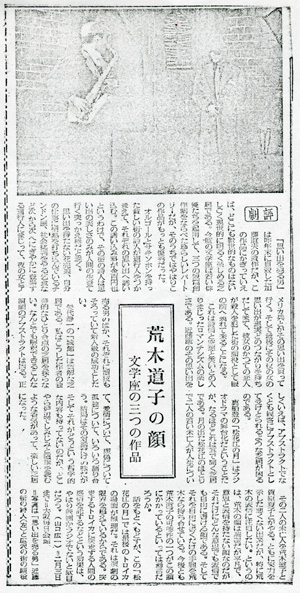 「思い出を売る男」は昨年末に自殺した加藤道夫の遺作だが、この作品にかぎっていえば、どこにも厭世的なものはないしごく現世的に明るく楽しめる芝居である。今度の文学座は若い俳優たちを起用して、三つの短編創作劇をならべた珍らしいレパートリーだが、そのうちではやはりこの作品がもっとも優秀だった。
「思い出を売る男」は昨年末に自殺した加藤道夫の遺作だが、この作品にかぎっていえば、どこにも厭世的なものはないしごく現世的に明るく楽しめる芝居である。今度の文学座は若い俳優たちを起用して、三つの短編創作劇をならべた珍らしいレパートリーだが、そのうちではやはりこの作品がもっとも優秀だった。