|
====七月の劇界展望==== 歌舞伎座では新派 菊・吉両座の対峙や新劇合戦にぎやか
[歌舞伎] 演舞場は菊五郎のいない菊五郎劇団で三日初日、明治座は吉右衛門が休みの吉右衛門一座で一日おくれて四日初日、演舞場が昼の部に黙阿弥の「小猿七之助」の通しを出せば、明治座は夜の「通俗西遊記」で勘三郎の長女久里子と次女千代枝、初舞台で幸四郎の三女れい子など子役十数名が小猿になつて小ザル競争、それだけでも足りずに演舞場は「たぬき」明治座は「鳩の平右衛門」を出してまるで動物くらべ、まず演舞場は、昼が既報の「小猿」のほか松緑の「船弁慶」夜が海老蔵の「盛綱陣屋」海老蔵と梅幸の「かさね」そのあとの「たぬき」は大仏次郎の新作 これは劇団員総出演で、死んだと思った商人の金兵衛(松緑)が焼場で生き返り、メカケ(梅幸)に御家人くずれの情夫(彦三郎)がいるのを知ったりして人に化かされてばかりいたのに憤慨、あべこべにタヌキになって人を化かすという風刺劇 明治座では「女殺油地獄」の勘三郎の与兵衛と幸四郎の兄太兵衛以外はオール初役ぞろいで、まず昼は先代左団次の当り狂言だつた綺堂の「相馬の金さん」を戦後初上演、上野の彰義隊に入つて切腹する江戸つ子の御家人金次郎を幸四郎がやり、寅之助を勘三郎、常磐津の師匠を訥升 次が狂乱物の「隅田川」を歌右衛門の狂女と勘三郎の船長で六代目以来の復活、あとの「油地獄」は勘三郎が四年前に三越劇場で訥升のお吉で上演したのを、今度は歌のお吉で再演、大詰の召捕もカットし花道へ逃げてゆくところで幕に改訂、夜は源氏物語後編の宇治十帖から北条秀司が創作して三年前に発表した「浮舟」がやはり話題になる、これは浮船(歌)をめぐる光源氏の子の薫大将(幸四郎)と匂宮(勘三郎)の恋のさや当てで、楽劇的だつた「源氏物語」とちがつて演劇的、次いで幸の「鳩の平右衛門」(女房は又五郎)最後の「西遊記」では勘三郎の孫悟空がカッポレを踊ったりして勘弥の猪八戒、福助の沙悟浄に幸の三蔵法師、歌の西梁国女王実はクモの精その他総出演 [新派] 歌舞伎座で五日初日、再脚色の「虞美人草」と「今年竹」を含めてオール新作のうち、まず昼は開国百年記念の「幻燈」(大仏次郎原作・北村小松脚色)という幻燈が初めて紹介されたころを背景に士族の商法や急進派対保守派の争いを描き八重子の弟の役で小堀誠の孫の彰(一二)が初舞台、次の「幸福さん」は源氏鶏太の新聞連載小説から伊馬春部が脚色したホームドラマで、花柳の心臓ばあさん花子が伊志井の丹丸と老いらくの恋で笑わせるはず 次が漱石の「虞美人草」を久保田万太郎が新脚色、八重子が高慢で我執と虚栄が強く最後に自殺する藤尾、伊志井が兄の哲学者甲野、古川緑波が新派初出演で外交官志願の宗近、紅梅が宗近の妹糸子、藤尾を失恋させて恩師の娘小夜子(赫子)と結婚する詩人小野は文学座の宮口精二を交渉したが、映画「七人の侍」に出演中なので同じ文学座の加藤和夫が代る 夜は四年前に死んだ京都の美人画の上村松園が大正七年四十四歳で「焔」を描いた前後を吉井勇が芝居にした「青眉抄」で、八重子が松園、その子信太郎(今の松篁で、この芝居の装置を担当)は初舞台の小堀彰の予定だつたが、小さすぎて十六歳に見えないので文学座の久門祐夫に変り すみれや一時祇園にいた英つや子たちが舞妓にふんして京舞「京の四季」を踊り、八重子も二役で芸妓になって「葵の上」を踊るほか、喜多村が演出を兼ねて竹内栖鳳、花柳が福助(後の梅玉)次が青春物シリーズ第五編「おばあちやんの青春」で英のおばあちやんが昔の恋人に会う明朗なお話、最後が里見弴の花柳物「今年竹」で花柳が主演、この興行から花柳の次男青山武嗣が花柳武始(たけし)と改名して幹部に昇進する [新劇] まず三日から十三日まで(十日は休み)読売ホ-ルでゴリキー生誕 八十五年記念に「エゴール・ブルイチヨフとその他の人々」を土方与志と山川幸世の協同演出で上演、十七年前ゴリキーの死んだ年に築地小劇場で追悼上演以来で、瀕死の富豪ブルイチヨフ(薄田研ニ)をめぐる親戚たちの争いを通じて十月革命の前夜を描いた物、中芸、泉座、俳優座、新協、プーク、東俳協、現俳の合同出演で、利根はる恵がムーラン以来久しぶりに舞台に出る 文学座が四日から十九日まで第一生命ホ-ルで上演する「夜の向日葵」は三島由紀夫がパリの旅宿で書いた戯曲で、長岡輝子が演出、南美江が、主役の未亡人柏木君子をやるほか三津田、中村、北城、仲谷らが出演、民芸は十四日から八月三日まで一ツ橋講堂で英国の劇作家ジェームス・バリーの「あつぱれクライトン」を福田恒存の訳で初演、滝沢は舞台に出ないで岡倉士朗と協同演出に当り、専ら演技と柔軟体操の指導を引受けている、清水が主人公の召使頭クライトン、ほかに宇野、山内、小夜、細川、高野らが出演 新協劇団は十五日から廿一日まで読売ホールで自主演劇で話題になった諸井粂次作「冬の旅」を村山知義の演出で上演、これは細菌製造の科学者を描いたもの 写真は(上)菊五郎劇団の「かさね」梅幸のかさねと海老蔵の与右衛門(下)右「女殺油地獄」勘三郎の与兵衛(下)左花柳武始(上)と小堀彰 |
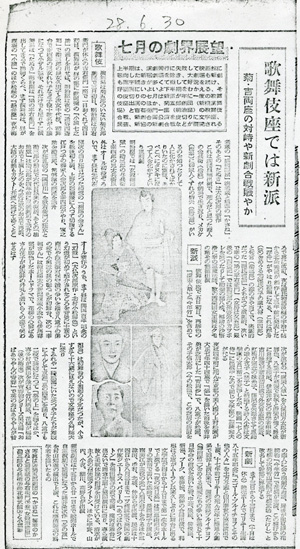 上半期は、演劇興行に失敗して映画館に転向した新宿劇場を除き、大劇場も新劇も黒字続きが多くて概して好況を続け、好調裏にいよいよ下半期をむかえる、その皮切りの七月は新派が年に一度の歌舞伎座出演のほか、菊五郎劇団(新橋演舞場)と吉右衛門一座(明治座)の歌舞伎合戦、新劇合同公演を皮切りに文学座、民芸、新協の新劇合戦などが展開される
上半期は、演劇興行に失敗して映画館に転向した新宿劇場を除き、大劇場も新劇も黒字続きが多くて概して好況を続け、好調裏にいよいよ下半期をむかえる、その皮切りの七月は新派が年に一度の歌舞伎座出演のほか、菊五郎劇団(新橋演舞場)と吉右衛門一座(明治座)の歌舞伎合戦、新劇合同公演を皮切りに文学座、民芸、新協の新劇合戦などが展開される