|
===劇信 花やかな狂言ずらり 際立った梅幸の実力===
[まず] 「太十」ですが二月の明治座と同様、チョボの鏡太夫と梅幸の品のある少年らしい色気と哀切可憐に満ちた十次郎が■■■く光ります。ついで海老蔵の久■■■役にぴったりして立派です福■■■菊、多賀之丞の皐月もまず■■■した。左団次の操は東京で■■■したが糸にのっているようで実は動きすきではないかとの疑問が今度も残り、余り好ましいものではありません。 [問題] は彦三郎の初役かと思われる光秀でしょう。まあソツのない出来で現在のところは二月の松緑に及ぶべくもありませんが、この劇団では案外、彦三郎の本役ではあるまいかとの閃きはありました。ただ心得顔に内面的に処理しようとするので如何にもウス手で光秀らしい重厚さ豪放さが全くないのです。まだ若いのですから、もっと熱っぽいものがほしかったことでした。最初の出のああ渋がった演技など賛成出来ません。(今の段階では)そのくせ竹槍の扱いに小細工があったりするのですが、九朗右衛門の正清はセリフのしまらぬのが難でした。 [左団次] の「素襖落」はたいして楽しくありませんでした。若手、中堅総出の「元禄花見踊」も十九人の総踊りが整っていた以外は平凡です。 「海老蔵」 の「直侍」はそば屋が見られます。権十郎の丈賀、鯉三郎、菊十郎のそばや夫婦とワキが充実しているためもありますが、あのうそ寒い情趣の中に海老蔵の美しさが、ほのぼのと燃えるからでもありましょう。また菊十郎の女房が、いかにも安店の女らしいのには毎度ながら感心します。彦三郎の丑松も異質でなく「それじやこれから兄貴にも」と直侍との渡りゼリフによく共感を残しました。 [大口寮] では梅幸の三千歳が終始、男を思いつめているのが印象的です。ただ清元を地にしての直侍と三千歳の動きに、この芝居独特な情緒がたかまったかといえば残念ながら、可成り遠いものでした。この意味では羽三郎の千代春に注目されます。 [左団次] (勘平)梅幸(おかる)権三郎(伴内)の「落人」でも梅幸の腕が判ります。左団次は「死ぬるその身を永らえて」で、さあこっちの番――とばかりに踊りだす古風な肌合には興味をもちましたが二級品の勘平でした。権三郎はただ生々しいので左団次とは似合わぬようです。 [さて] 通し狂言は劇団、三度目の「白浪五人男」ですが、海老蔵の弁天小僧、梅幸の赤星十三、坂東彦三郎の南郷力丸、福助の千寿姫や橋蔵の幸之助それに八重之助以下の殺陣の面々がよく、左団次の日本駄右衛門は姿だけ、九朗右衛門の忠信利平も風貌のよさにうらはらな、しまらぬ演技でいま一息でした。幕々では、弁天小僧が立腹を切る極楽寺屋根上の立回りが素晴らしく、ついで初瀬寺の花見が歌舞伎らしく賑います。 [意外] だったのは浜松屋がごくつまらなかったことで海老蔵といえば序幕の花見の信田小太郎、実は弁天小僧の花道の出の歩みぶりに実は市井の徒らしいカゲを匂わせる上昇があったのですから、浜松屋が好くないのは不思議な位です。疲労があったのでしょうか。(十六日目所見)=大鋸時生=(写真「白浪五人男」初瀬寺花見の場面) |
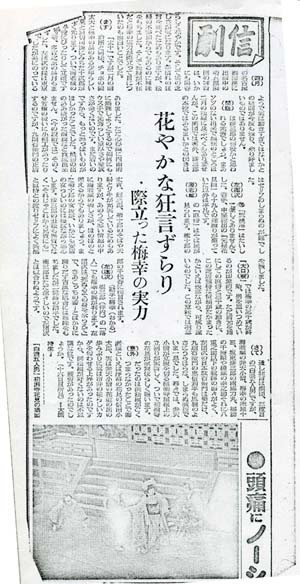 [四月] の名古屋御園座に出演中の菊五郎劇団の舞台は、いかにも陽春らしく花やかです。そして実の乏しさが気になります。手慣れの狂言を並べたためもありますが、松緑の不参加からでもあるのに興味を持ちました。そして松緑が不在だと梅幸の実力が際立って目についたのも面白いことでした。
[四月] の名古屋御園座に出演中の菊五郎劇団の舞台は、いかにも陽春らしく花やかです。そして実の乏しさが気になります。手慣れの狂言を並べたためもありますが、松緑の不参加からでもあるのに興味を持ちました。そして松緑が不在だと梅幸の実力が際立って目についたのも面白いことでした。