|
====演舞場の文楽因会・評 浜村米蔵==== 枯淡な芸境が描く「沼津」
どうぞできるだけ目出度く無事にというのが、やはりわれわれ見物の「今日の御祈祷」である ○・・次は「先陣館」を前が相生太夫、後を津太夫で、歌舞伎と比較する興味はあってもちつとも精彩がない。問題の伊達は合三味線が広助と極って「昔八丈」を出している。キレイなノドを聴かせるだけのもので損だ。続いて綱太夫弥七の「重の井子別れ」で、これが昼の唯一の聴物だが、前の双六の件がカットされているので物足りない。 あとは「炬燵」で「藪に夫婦の二股竹」までを松太夫、奥を宮太夫改め和佐太夫が語る。 ○・・第二部は「車曳」雛、長子、南部たちの掛合で始まる。三味線は清八、これでは玉五郎の櫻丸が目を引いた。次が松太夫の「朝顔日記」で清六の糸に導かれて、丁度手ごろの語物らしく本領を発揮する。 新作にろくなものがないのは通り相場で「出陣」はその見本みたいなものだ。 第四が「沼津」この一段に今の人形芝居の全景観が、ながめ渡されるといっても過言ではない。前を綱「お米はひとり」から山城である。本当はこの全一段を紋下にやってもらいたいところだが、それはもう体力が容さない。山城■■の浄瑠璃は心理主義というか■■主義で、近代写実の影響を受け■いる。綱は無論この師匠の解釈を継承しているといっていい。 平作の断末魔の「なむ」とむせび泣くような念仏にも、かなり繊細な気分心持がひめられている。全休が平面描写の感じのうちにそういうものがある。とにかく伝説神話から開放された浄瑠璃である。大切は「阿古屋」で伊達と津の掛合、寛治郎の三味線が腕によりをかける。 |
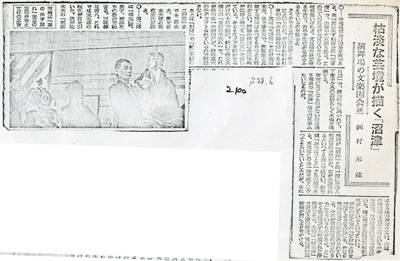 ○・・新橋演舞場は因会文楽である。第一部は先ず掛合の「三番叟」で、山城や文五郎も出る。この二人の長老が元気なのを見るのは有難いけれど、文五郎の翁が寄る年波で、首や手先のぶるぶるふるえているのを見ると
○・・新橋演舞場は因会文楽である。第一部は先ず掛合の「三番叟」で、山城や文五郎も出る。この二人の長老が元気なのを見るのは有難いけれど、文五郎の翁が寄る年波で、首や手先のぶるぶるふるえているのを見ると