|
====戯曲生産への緒(下) 八田元夫====
同時に、この客観的情勢の驚くべき劣悪さは、後に続くものを全く絶ってしまった。若い世代は文化、特に、本質的な演劇からはあらゆる意味で遮断されてゐた。若い作家を生み出す豊穣な土壌は何処にも見出されなかった。劇作を志すにしてもとつかかりさへ見出し得なかったのだ。―――然し、それはよき作品を生み出したい意欲が跡を絶ったことを意味するものではない。―――数日前のこと、戦時中を、最も強靭に生きぬいて来た作家の一人、三好十郎が、自宅で戯曲研究会を開設、会員を公募したところ、旬日にして百数十名の新人応募者があり、その銓衡のため、一堂に会したところ、三好の家の根太がぬけて了ったと、きかされたが、こんな話にしてからが灯を継ぐ意思は、既に盛んに燃えたぎらうとしてゐるのを物語るものだ。文化新日本の建設を前にして、かかる燃え上りを如何にして高まらして行くか、書きたい新たなる意欲のあらはれに対して自らのみの徹底的取返しに目覚めた部分が直結して、若い運動を展開するところに、新しい戯曲生産の緒があるのではなからうか。(筆者は演劇人) ====みどりの鯛 花柳章太郎==== わたしは、毎日焼跡の道頓堀から千日前の歌舞伎座へ通ってゐます。 中座の外廓、それも楽屋の背中になっている赤い煉瓦に昔そのままの窓の扉がついているばかり、法善寺境内の敷石が残ってゐて、さだかにそれと判るくらいの惨めな姿になった中に、ニョッキリと立つ石の不動尊。 戦災前まで水苔の濡れた立像の前に、ぬかづいて祈願してゐた人達の姿がいまでもそのまま眼の底に残ってをります。 「鮮魚、みどり」の行燈の灯影がそこらの御影石の、それも流れるやうな打水の上に投げられてゐるのも忘れられない記憶の一つです。 大阪へ震災後四、五年いってゐたころ、またその後東京へ帰ってからも年一、二度は道頓堀へ出勤がきまると、その初日の朝は、先代みどりの主人が眼の下に二尺ぐらゐの鯛を必ずお祝ひに下さったものでした。 鴈治郎、長三郎、扇雀、梅玉、福助、延若、市蔵、らの大阪土着の人、東京では、歌右衛門、福助、羽左衛門、家橘、幸四郎、左団次、菊五郎などが。新派では伊井、水谷、藤村、私などがひゐきで、旧の方では吉右衛門、新派で喜多村、河合、井上の人々がぬけてゐる。極端に好き嫌ひのあった人だが好きとなるとその人の欠点までことごとく好きでひゐきにした人でありましたが、惜しくも二十年ほど以前になくなられたのです。子福者で大勢のお子さんがあって男の方は応召され、女の方はご主人亡き後、看板をうけ継いでさらに出店を多くひろげました。 私はそんなことを思って三月十三日以後のその店がどうなったか心配しております。われひとともに終戦以前以後もその消息を絶たれ、多くのひゐきの方たちの行方がしれません。 大阪へ来て不自由な中をどうにか毎日の主食に事欠かない□□□いつもの見事□□□大阪の時の日の□□□ことを、その声□□□合掌してゐます□□□者は新生新派□□□・・・・・・・・ |
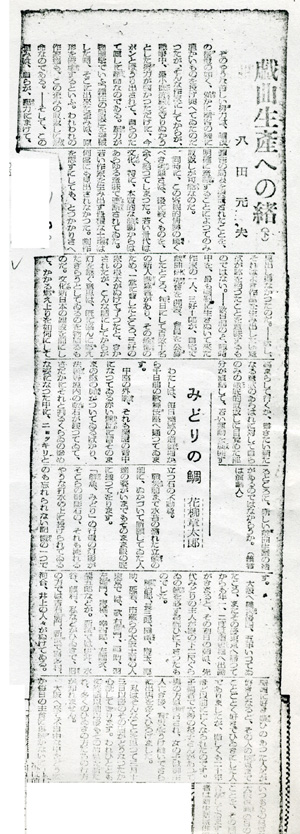 そのやうな苦しい努力は、曙夜の微燈の如く、僅かに顧客の胸に温かいものを投げ与えてゐたのだったが、そんな作家にしてからが、戦争中、最小抵抗線を守りぬかうとした努力が強かっただけに、今ポンとほうり出されて、自らのたて直しに懸命なのである。圧力が物理学でいふ「弾性の局限」を突破した時、そこに出来た歪みは、原形を破壊するといふ。われわれの作家達も、この歪の取返しに懸命なのである。――そして、この歪は、自らが、圧力にまけて、弾性の極限を突破されたことを、明確に意識することによってのみ取返しが可能なのだ。
そのやうな苦しい努力は、曙夜の微燈の如く、僅かに顧客の胸に温かいものを投げ与えてゐたのだったが、そんな作家にしてからが、戦争中、最小抵抗線を守りぬかうとした努力が強かっただけに、今ポンとほうり出されて、自らのたて直しに懸命なのである。圧力が物理学でいふ「弾性の局限」を突破した時、そこに出来た歪みは、原形を破壊するといふ。われわれの作家達も、この歪の取返しに懸命なのである。――そして、この歪は、自らが、圧力にまけて、弾性の極限を突破されたことを、明確に意識することによってのみ取返しが可能なのだ。