|
====芸界覚え書 京舞の躍進ぶり==== 余勢かって大阪公演 禅坊主のような修行
祇園芸者稲子の抱えとしてまだ十一、二歳、舞妓で出て間もなく先代井上八千代の目にとまり、この妓ならばと稲子に所望して養女に貰って舞踊の後継者に鍛えあげられてここに四十年愛子時代に会館のコケラ落しに三番叟を舞うて鴨東第一の称を博し、井上八千代を襲名して今日に及んだ回顧に感慨も浅くなかろう。 八千代が幼時、貰われて来たころから年ごろになるまで先代の仕つけは実にきびしかった。一切手をとってけい古などはしない。そうして芸者連のけい古をジッと見ているだけで井上流の骨法を会得せねばならぬ。不言不可説まるで禅宗坊主のような修行を積んだものであったそうだ「この児救うべし」と見込んだ先代八千代のケイ眼もえらかったが、師であり母である先代の名を恥かしめなかった八千代もまたえらい婦人である. その上に松本のお佐多という女の大久保彦左衛門がいる。先代の相談相手で最高の弟子であり祇園切っての大御所である。この人が常に今の八千代の後見役、意見番としておさえていて一々この人の指図に従わねばならぬ、お佐多は八十歳でも中々元気で流儀のために出精し、昨年の井上流東京出演にも出かけたし、家元より一足先に受賞している。 このお佐多の案かどうか知らぬが近ごろ井上流に一大変革が断行された。今までは芸者にはいくら上手でも名取りを許さなかったし、又祇園以外に弟子取りもしない。もちろん男の弟子などはなかった。しかるに近年芸者にも名取りを許るすことになり、素人にも、また男子にも井上流を伝えることも許すようになった。 今まで一廓に納めてジッと掌中の珠玉を保っていたようなことは封建的でありとしてかく門戸を解放し、流儀の弘通を図ったものであろうかと思われる。これは考えようによっては大いに奨励すべきことでもある。 ただ他流に見る枝から枝へとひろがっていってその中にも家元が若干派生する。これもまたまぬがれぬ時代の勢いではあろうが自然に根幹を忘れ、流儀の真ズイが歪曲されてしまうような結果になっては伝統を重んじて来た京舞にとって慶すべきことではない。この点をある程度で引締めてこの道を歩んでほしいものだと或る舞踊好きの話。(この項つづく)(浦 山吹) |
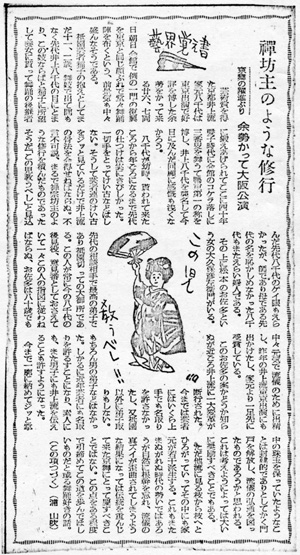 芸術賞を得た京都井上流家元八千代は東京出演で好評を博した余勢をかって来る廿六、七両日朝日会館で例の一門の復興を東京と同じ顔ぶれで堂々舞踊陣を布くという、前景気も中々盛んなそうである。
芸術賞を得た京都井上流家元八千代は東京出演で好評を博した余勢をかって来る廿六、七両日朝日会館で例の一門の復興を東京と同じ顔ぶれで堂々舞踊陣を布くという、前景気も中々盛んなそうである。