|
====歌舞伎座・評 富田泰彦==== 見事な「曽根崎心中」 「高野聖」効果に疑問残す
今興行中、幾多の問題をなげかけ、好悪ともに批判の中心となろうと思われるのは泉鏡花原作「高野聖」の上演である、吉井勇脚色、久保田万太郎演出、それに福田蘭童作曲、藤間勘十郎振付、織田音也装置、篠木佐夫照明という物々しいスタッフをそろえ、莫大な費用を投じられたであろうが果してそれだけの効果があがっているかどうかを疑問とせざるを得ない――元々、原作にしてからが一旅僧(高野聖)の旅宿におけるロマンチックな物語にすぎない、鏡花一流の妖怪めいた神秘主義的なものを劇化するには彼のシェクスピアの「真夏の夜の夢」と同様人間と妖精とのからむ夢幻詩劇風なものにせねばならぬことはまず常識である、洋楽を用い独唱を入れ、放送効果の擬音をも配して、暗転のつなぎなどに試みてはいるが、それが十分に消化されているとは義理にも申しかねる × × 歌舞伎音楽としては、将来洋楽ならではある戯曲によっては表現しかねるというのは小林一三氏の持論である、音階の狭い邦楽よりもオクターブ(音域)の広い洋楽の効果的に優っているからだ、出演俳優はいずれも努力している、扇雀の雪路は女優でないシガを或程度かくしてはいるが「かかる霊水で清めたこういう女の汗は、薄くれないになって流れよう――」という本文の味があの水浴のところではシンミリと出ていない、簑助の僧宗朝にしても「聖」という文字にとらわれて行いすましているのでは恐怖心も妖気もただよわない、雷蔵の白痴の男は、花形俳優にしてあのイヤな役を引受けた度胸を買い、訥子の老爺は一番この戯曲の焦点をつかんでいるのと、栄治郎の猿が結局観覧席の憂鬱をさらって大受け――しかし、これも無名の子役ではこうも喜ばれまい × × 夜の部は例の「お団と五平」は「高野聖」とともにこの劇場独自の大舞台こそまことに日本一だ、簑助の友之丞はじめ延二郎の五平、鶴之助のお国の三優とも、この動きの少くない脚本の味を十分に納得せしめたのは偉とすべく、次に矢張三優競演の「鎌倉三代記」では富十郎の時姫は予期以上によく、鴈治郎の三浦之助、寿海の高網という順は、公平な見方である、――ただこの狂言は大舞台が禍いして三浦が井戸から呼び込んで、二重へよろけながら戻って来る距離が長いので、せっかく極まりの型も不自然になるのは気の毒だ、吉三郎は富田の役で出たのは如才ない此優柄はわかる気がする × × 第三は、寿三郎受賞記念の「楼門」に寿海の久吉を得て久々の双寿顔合せの大舞台で好劇家を喜ばす、延若没後の五右衛門はこの優の専売で舞台顔の立派さも買うが、矢張延若との時代の距りはなくとも身についた滋味はなお稀薄といえば酷評か、ついでながら奥山の中納言が丸裸での花道の引ッ込みは、矢張り昔通りの差しかけ傘で行かねば役の性根は失せる × × 第四近松原作、宇野信夫脚色演出「曽根崎心中」三場は「昭和歌舞伎年代記」にも録さるべき鴈治郎、扇雀父子の名誉の狂言、東京でも二回好評を博し京都も済みて大阪へははじめて今度上演したものだ、すでに劇通待望のもので、しかも、洗練に洗練を経て来たもの、鴈の徳兵衛の意気込みの一段すざましいのは当然だが、扇雀のお初の美しさに加えての情意が囗囗囗た演技の妙は、さすがに「毎日演劇賞」の審査に狂いはない、とくに近松の技巧を弄した天満屋の場といい、天下の名文と知られた心中場を劇と振り事との間を不即不離的に演出したことや、天満屋へ簑助の久右衛門を出した運びなど原作の単純さを見事に劇化している、この狂言の趣向は、後の「梅忠」冥土の飛脚の大和屋のくぐり戸を開ける動作や、二階と縁の下との相違こそあれ、吉三郎の九平次の悪態もイヤ味なく好演である × × 要するに関西歌舞伎でもこうして各俳優がさらに協力的に出れば天下恐るるものなしか、是非今度問題となった新作や、評判の名狂言を一般観衆も再認識してほしい、最後に本紙がかつて座談会で指摘した劇場の観客サービスも改善され、幕間も十分に余裕ある上に、夜の打出し時間を九時四十分頃にしたのは、郊外からの客の便宜のために大賛成である |
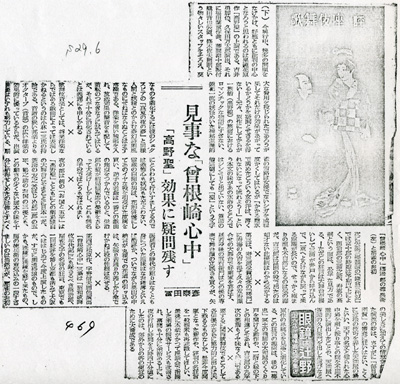 (下)
(下)