|
====劇評 大阪歌舞伎座の吉右衛門劇団==== 「浮舟」は配役の勝利
吉右衛門は昼の部の「寺子屋」での松王丸と、夜の部の「摂州合邦辻」での合邦の二役だが、これはあきらかに後者の合邦を採るべきだろう。老役の有難さには足の不自由さもさして気にならず“泣かねど親の慈悲心を”の沈痛感から“幽霊もさぞひだるかろう”のあたり含蓄あるセリフまわしの妙味がさすがに吉右衛門である。 歌右衛門の玉手御前は古風さと気品との合流したこの人の持味に格調があった。時おり心理的な追究の意味で、上手屋台へ眼くばせするわずらわしさはむしろ芸の若い証拠なのだろうが、前半では“顔と顔とは距たれど”の戸口での形、後半では“いっそ沈まばどこまでも”の動きなど、いずれもすぐれて美しい。 なお、この玉手御前でつけ加えておきたいのは片そでをもぎ取られた衣装の好み。もちろんこれは従来からある歌右衛門系の好みなのだが、下着の原色の赤地がちらほらするのは、この一幕に流れるいぶしのかかった色調を乱して目ざわりである。梅玉系の無キズの黒地にしかない。 「寺子屋」では吉右衛門の松王丸が気力に欠けている。いろは送りのあたりにこの人の本質的な断片がうかがえるにしても、病弱のせいで演技のイキが断続するようである。幸四郎の源蔵も尋常ながら尋常以上を出ていない。この一幕では宗十郎の戸浪がよく、歌右衛門の千代とともに二人の女形に軍配があがる。 幸四郎では「暫」の権五郎景政が予想以上にしっかりしている。ツラネの調子では先代をはるかに抜いているし形もととのっている。ついでは宗十郎の照葉を佳作としたいが、勘弥のなまず坊主や吉之丞以下の腹出しにも少しシャレッ気があれば、さらにこの一幕は楽しめたであろう。問題は別になるが歌舞伎十八番の「暫」を開幕劇なみに扱う近ごろの傾向は当事者の遠慮勝ちな思いすごしか、それともこれは歌舞伎の現代的敗北なのであうか。 新しい所作事の「髭櫓」は勘三郎の愛きょうで支持されている。ふざければふざけるほど愛きょうになるところ勘三郎の一得だが、舞踊劇としての内容からすればかなり乏しいものだ。幸四郎の奥方が珍品でもあり器用でもあり、団之助の老いたる女立衆はどっか岡本一平えがく漫画を連想させた。 新作では北条秀司の「浮舟」■注目されるべきである。作者は■神と肉体との相剋において源氏物語を近代的な解釈へ導入しようとしている。そして肉欲が精神に■ち勝つ悲劇に人間の秘密を衝いた結末も、平俗ながら今日の観客に同感があろう。少々ばかり時間がかかり過ぎるのと、薫大将の精神主義に説明が足りなくて観念化しているほかは、これだけの構成の確かさもこの作者の手腕である。 さらに、この作品は幸四郎の薫大将、勘三郎の匂宮、歌右衛門の浮舟と、適材を適所にはめ込んだ配役の勝利だったといえる。もちろん演技の細部には多くの疑問もあるにはあるが、この三人三様の個性的なものを、作者がよく発見し得ているからである。 長谷川伸の「刺青奇偶」は相変わらず前半のスピーディな運び方が・・・・・・・・・ |
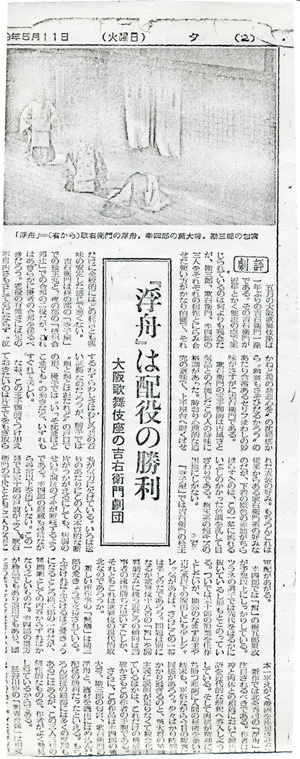 五月の大阪歌舞伎座は一年ぶりの吉右衛門一座である。その吉右衛門が近年とかく健康の点で案じられているのは何よりも残念だが、勘三郎、歌右衛門、幸四郎の三人をそれぞれの個性とにらみ合せた使い方がかなり的確で、それだけに全般的にはどの狂言とも興味の安定した感じで悪くない。
五月の大阪歌舞伎座は一年ぶりの吉右衛門一座である。その吉右衛門が近年とかく健康の点で案じられているのは何よりも残念だが、勘三郎、歌右衛門、幸四郎の三人をそれぞれの個性とにらみ合せた使い方がかなり的確で、それだけに全般的にはどの狂言とも興味の安定した感じで悪くない。