|
りゃ聞こえません、みなさま方」。行動派歌舞伎ファンの行状記、「知らざあいって聞かせやしょう」。 【河東節連中】 〝特訓″助六のパトロン 時は春、所は吉原。舞台は上から桜のつり枝が下がり、正面右手には「三浦屋」と白く染め抜いた柿色ののれん、左手一杯は朱色の大格子が広がっている。ごぞんじ歌舞伎十八番の一つ「助六由縁江戸桜」の幕開きである。しばらくするとかみしもをつけた役者が現 れ、見物に歌舞伎十八番上演の口上を述べ、こんどは大格子の奥に向かって、「河東節御連中様、どうぞお始め下されましょう」といって奥に入る。 ^^春霞、たてるやいずこ三芳野の、山口三浦うらうらと…… のどに自信のある歌舞伎ファンが出演する一風変わったしきたりがある。それも団十郎系の「助六」だけ。 松坂屋社長の伊藤鈴三郎さん(70)も河東節連中の一人。得意は清元と小唄だが、亡くなった十一代目市川団十郎の襲名公演の時に財界人の仲間から誘われて、「助六」の特訓を受けたのが始まりだ。この時は東京だけでなく、名古屋の公演にも三回ほど出た。その後、 現在の市川海老蔵の襲名にもかり出されている。 河東節は一中節、薗八節、荻江節と並ぶ古曲で、江戸浄瑠璃の一派。技法もむずかしいので伊藤さんのように長唄、常磐津、清元などの下地のある人でないと、興味も生まれないし、こなしきれない。 二月の歌舞伎座に先月亡くなった作家舟橋聖一さんの「絵島生島」が出ている。劇中劇に「助六」をはさんだ舟橋さん、「前は清元でやったが、こんどはぜひ河東節で」と希望したそうだ。舟橋さんの河東節好みは有名。伊藤さんは舞台裏で目の不自由な舟橋さんと隣り合わせ、本をめくってあげることもあったが、「見ないでも語れるようだった」と感心する。 もちろんギャラなど目もくれない持ち出し出演だが、黒紋つきで大格子のすだれの後ろにすわる気分は何ともいえないものらしい。日本団体生命保険相談役の花岡俊夫さん(86)をはじめ大企業のトップや銀座の老舗の主人、文化人など多彩な顔ぶれだ。 昔は「舞台へ顔を見せたくない」と、すだれの後ろで語ったのに、「目が細かすぎてつまらない」という〝御連中″もいて、大道具が竹を一本置きに抜いたというエピソードもある愉快な仲間。「僕は東京育ちなのに、名古屋なまりがあるといわれる」と頭をかく伊藤さんも、「こんど助六がかかったらまた」とヤル気十分のようだ。 (写真)市川海老蔵の「助六」-左手の大格子の裏に河東節連中がいる 【大向こう】 三度の飯より三階席 花道の揚げ幕がチャリンと鳴る。間髪をれず、三階席から声が掛かる。「音羽屋ッ」。観客は花形役者の出に胸を躍らせる。歌舞伎に掛け声はつきもの。舞台中央で役者が目をむき、大きく見えを切った時、声が掛からないと決まらない。三階席――大向こう。ここには「三度の飯より芝居が好き」な人たちが陣取っている。 白浪五人男ではないが、「がきのころから芝居が好きな」三新産業取締役の浦尾文雄さん(56)、佐賀の生まれで、昭和二十四年に東京へ転勤。「大一座を見られる」と張り切って上京した。もっぱら三階席に通いつめ、そのうち松本幸四郎の「番町皿屋敷」に感激し、思わず「高麗屋ッ」とやった。 一声ピタリと決まると度胸がつき、一時期は「ありゃセミプロだ」と勘違いされるほどだった。その浦尾さんの声が聞こえなくなってしまった。「このごろ一階席へ行けるようになったら、どうも気が引けて」と三階席時代を懐かしむ。ほれ込んでいる中村雀右衛門が登場しても「京屋」という声がかからないと寂しくなるという。 「やはり三階席がいい」、というのは熱狂的な中村芝翫ファン、新興出版社啓林館東京支社の小川智さん(38)。以前は会社の忘年会で歌舞伎見物に行っても退屈して居眠りしていた口だが、「日本人の教養として勉強しよう」と一念発起。国立劇場が開場した昭和四十一年秋から、コーヒーで目を覚ましながらがんばっているうちにとりこになった人。 そのきっかけが「雷神不動北山桜」、当時はまだ福助だった芝翫の雲の絶間姫で、どうしても「成駒屋ッ」といいたくなった。芝翫の出る日は、月に十五、六回見に行く。ある時、花道のそばでじっくり見ようと、一等席を奮発したが、お目当てが出る時間になったら、我慢が出来ず三階席にかけ登って声を張り上げていたとか。 小川さんの仲間で大向こうの集まりの一つ歌舞伎弥生会の吉川経造さん(59)は「私設応援団だ」と笑う。 とにかく大向こうはケタ外れの人が多い。ニトムズの営業マンの清水俊男さん(26)は就職前に二十五日公演で二十三日通つたというし、幕あいは水ばかり飲んで、のどをうるおしたり、テレビ観劇でも声を出したり。顔を合わせる たびに「松島屋はいいが、天王寺 屋は長くてむずかしい」「しかし関西では伸ばす人が多いから」などと三階でガヤガヤやっている。 (写真)掛け声談議に花を咲かせる、左から清水さん、吉川さん、小川さん やってみてこそ面白い 早稲田大学教授 郡司正勝 歌舞伎は参加の芸能だ。演者と観客が一体になって、初めてドラマが生まれるる。それを西洋の近代劇と同じように、芸術鑑賞よろしく〝拝見″するのでは面白いはずがない。眠くなるのが当然だ。参加の要素は日本の芸事の特色でもある。邦楽も踊りも、また茶道や生け花でも、見るより自分でやる方が面白いし、やってみて面白さがわかる性質のようだ。 現在の芝居には、そうした一体感がなくなっている。観客は大変お行儀がいい。大衆の感覚から生まれた歌舞伎なのに、与えられたものを見るという姿勢だ。もちろん観客を感動させるのに十分な芝居をしていない役者にも責任がある。しかし義理で見ているような観客ばかりではそうなりがちだろう。 襲名という習慣も、ひいきの参加が作り出したものだ。先代より芸は未熟でも、「ひいきにして育ててやろう」という観客で成り立つのが襲名だ。見るねらいも違う。今の人は「源氏店」を見に行くが、昔なら羽左衛門の与三郎を見に行った。作品ではなく役者の芸に関心があった。だいたい筋ばかり追っても、歌舞伎はつまらない。 そこで、いいと思えば思わず「橘屋ッ」と声が出る。大向こうのあり方にはいろいろ批判もあるにせよ、参加という意味では、その先端部分だ。義理で機械的に掛けたり、よく芝居がわからないで間をはずしたり、腹が立つケースも少なくないが、本来はもっと純粋だったし、今でもうれしくなるような時がある。 河東節には「自分たちが後援者だ」というプライドと、「どこまでも素人だ」という精神、要するに江戸っ子の心意気がある。だんな芸で庶民とはちょっと離れた上品なものだが、歌舞伎の役者と観客の交流を端的に表している。邦楽に通じていた昔の観客は、「まずいな」と思いつつ、覚悟して聞く遊びの精神を持ち合わせていたといえよう。 もちろん、大向こうや河東節は特別なものに過ぎない。しかし、こうしたものに見られる積極的な姿勢が観客の側にないと、参加の芸能としての歌舞伎はますます退屈なものになってしまう。玉三郎が登場する時の客席のどよめき、そんな熱気が舞台を盛り上げるのである。 |
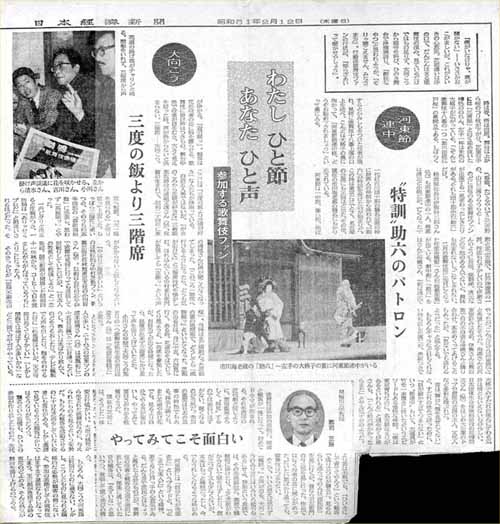 「僕がいなけりゃ、幕が開かない」――いささかおこがましいが、これがひいきの心意気。芝居通いは序の口で、だんだんはまる歌舞伎の深み、見ているだけではもの足りず、大向こうから屋号を叫び、ひのき舞台で浄瑠璃語り、「酔狂なやつ」と思われようが、「そ
「僕がいなけりゃ、幕が開かない」――いささかおこがましいが、これがひいきの心意気。芝居通いは序の口で、だんだんはまる歌舞伎の深み、見ているだけではもの足りず、大向こうから屋号を叫び、ひのき舞台で浄瑠璃語り、「酔狂なやつ」と思われようが、「そ