|
そうした明るい前途を背負って、二人仲良く東上したのが、今月帝劇の関西歌舞伎引越し興行。だから、今度の「忠臣蔵」で、ちょっと眼のこえた歌舞伎フアンなら、寿海の勘平、鴈治郎の判官、簑助の師直、富十郎のおかる、寿三郎の由良助などはさておいても、先ず扇雀の小浪、鶴之助の力弥を期待したであろうし、二人のお目見得狂言ともいうべき「落人」のおかる・勘平に多大の関心を寄せたに相違ないのだ。 そして、その期待は十中、八、九まで満たされたといつても過言ではない。鶴之助など、役柄の関係もあつて、日ごろの真価をもう一つ発揮できなかった憾みはあるが、それでも、このコンビのセリフ回しのたしかさだけは、十分認められた。大阪の黒幕といわれる武智鉄二のムチに鍛えあげられた、それがいわゆる「花形歌舞伎」の財産でもあるからなのだろう。 「こつちは眼を回し通しでした。イキをつめて中間六尺を見ると、自分は何も思ってなくても、観客からはその思い入れがちやんと分る――つまりセリフのイキをやかましくいわれたんです」(扇雀)、「イキの吸い方、つめ方など、声の使いわけをトコトンまで教えこまれました」(鶴之助)。と、当人たちも異口同音にその間の苦労を物語る。 扇雀は昭和六年の生れだが、幼くして祖父先代鴈治郎の物真似に秀でていたというから、やはりセンダンは二葉より香しの類。扇雀より二つ年上の鶴之助も吾妻徳穂を母に持つ関係からこれまた祖父に当る先代羽左衛門の血を引く天才的キリン児。隔世遺伝といわれては父親は立つ瀬があるまいが事実、扇雀の父鴈治郎にしても、鶴之助の父富十郎にしても、今では息子の人気にオンブしている格好なのだから止むを得ない。 梨園で言うところの御曹司として過不足なく育てあげられた二人、「武智歌舞伎」の申し子的存在――すべて相似た環境に置かれている二人だが、その実、一皮むけば少からぬちがいが出てくる。 「恐怖時代」の伊織之介が大当りに当った祝賀会の帰途、ホロ酔い加減も手伝って原作者の谷崎潤一郎大先生をつかまえ、いきなり握手を求めたという扇雀の無邪気さ。しかし、それにはそれだけの理由があつて、躍進の足がかりとなつた実験劇場の初公演(昭和廿四年十二月)以来、すべてに恵まれた星の下にある扇雀と、公私共に境遇的にはかなり難しい立場に立たされた鶴之助とでは、周囲の風当たりも自ずとちがつてくるのだろう。好きなカメラをいじくつていても、新型の自動車を乗り回していても、鶴之助にはどこか、ニヒルなカゲがつきまとつている。大仏次郎作「楊貴妃」の高力士に一種異様な持味が漂っていたというのも、だから、うなずけないことではない. 扇雀は「お役者小僧」と「魔剣」で、鶴之助は「次郎長一家罷り通る」と「江戸姿一番手柄」で映画の面にも殆ど同時に進出したが、世評は何れも香しくない。若い二人にとってはいい薬だが、これからが、むしろ、もまれどきであり、勝負の別れ目でもある。はるかなるゴールに達するまでには、前途必ずしも多幸とばかりは限るまい。(花道人)=絵は松木ひろし |
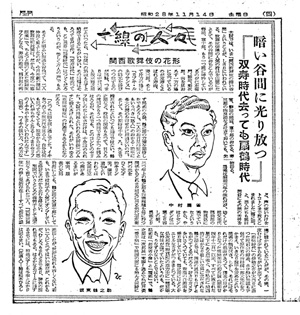 大阪では、いま「関西歌舞伎の暗い谷間」ということが、しきりにいわれている。歌舞伎俳優の人気の消長を山脈にたとえて、その谷間におちこんでいるのが簑助、富十郎。もう一つ底に呻吟しているのが仁左衛門、雛助、菊次郎。谷を見下ろす一方の峰に立っているのが双寿とよばれる寿海、寿三郎。そして片方の峰に「カブキ・ルネッサンス」の陽光を浴びつつ位するのが扇鶴、つまりは中村扇雀と坂東鶴之助だといったら、「谷間」の語源も自ずと納得できるにちがいない。その扇鶴はそろってまだ廿代。「双寿時代」は去っても、ここ当分「扇鶴時代」はつゞくだろうというのが、等しく万人の声でもある。
大阪では、いま「関西歌舞伎の暗い谷間」ということが、しきりにいわれている。歌舞伎俳優の人気の消長を山脈にたとえて、その谷間におちこんでいるのが簑助、富十郎。もう一つ底に呻吟しているのが仁左衛門、雛助、菊次郎。谷を見下ろす一方の峰に立っているのが双寿とよばれる寿海、寿三郎。そして片方の峰に「カブキ・ルネッサンス」の陽光を浴びつつ位するのが扇鶴、つまりは中村扇雀と坂東鶴之助だといったら、「谷間」の語源も自ずと納得できるにちがいない。その扇鶴はそろってまだ廿代。「双寿時代」は去っても、ここ当分「扇鶴時代」はつゞくだろうというのが、等しく万人の声でもある。