|
===劇評 山口広一=== 大仏次郎の作品 十一月の大阪歌舞伎座
さて、その時代物狂言としての「金閣寺」だが、この一幕を魅力あらしめたものは、やはりなんといっても海老蔵の役者ぶりのよさでなかったか。その久吉は演技の密度からすれば必らずしも高い評価に達していなくとも、顔、声、姿の三条件を美の拠点とするこの種の役柄において、今日の海老蔵はすでに今日の歌舞伎役者の最高を示し得ている。それは演技以前の、むしろ役者個々の先天的ないし生理的な条件に多く支配されるものだろうが、歌舞伎ではこれらを一般に“役者ぶり”と称してその魅力の基準とするのである。 松緑の大膳も幅のある押出しにものをいわせて一様に佳良だが、ただ全体の調子が平明に過ぎて単調なのが惜しまれる。いい替えればこの大膳は久吉の“善”に対する“悪”の象徴として一種ホリの深い陰影を要求する役柄だからである。福助の雪姫は少々ばかり荷が勝ちすぎた感じ。左団次の直信がさすがに古風な味で本役だった。 「三人吉三」をワキ筋の文里一重まで加えての通し狂言としたのは珍しく、今日黙阿弥もの、特にその世話狂言の復活と伝承とは菊五郎劇団の一つの大きい努力として敬意を払う。 もっともこの劇団の平均年齢はなお若い。それだけに肝心の「大川端」などいささか空虚に終ったのが残念である。梅幸のお嬢吉三はどこやら燃焼するものが足りない。海老蔵のお坊吉三も平凡。この二人に比べると松緑の和尚吉三が演技としては最も整っていてその実力をうなずかせるが、むしろこうした主役どころよりも相変らず照蔵の久兵衛や菊十郎の夜鷹などの端役が光る。そしてそれらが少なくとも黙阿弥の世界の残香を感じさせている。今日での貴重品である。 以上二つの古狂言とあざやかな対立を見せて大仏次郎氏の「築山殿始末」がまことに新鮮である。 これは家康の子の信康が時代と環境の犠牲として自決するまでの悲劇。同じ作者の前作「若き日の信長」に引続いて、こでも孤独で善良な人間の苦しみが描かれているのだが、劇的な契機の積み上げ方においてさらに前作にまさるものがある。特に信康の母親の築山殿と信康の妻の徳姫と二人のヒステリー女性がいがみ合う「岡崎城内」の場が面白く出来ているのと、信康が愛人の小笹を発見する「城外の池」の場の明るい美しさがすぐれた快感である。 演技では梅幸の徳姫を第一に推したい。あの冷やか表情の裏によどむけわしい性格を見事につかんでいるからだ。海老蔵の信康は如何にも素朴だが、その素朴さがむしろ作意なのであろう。松緑の家康、左団次の築山殿も悪くない。 大仏次郎氏の作品は常にあの清澄の気品に得がたい創意がある。そしてそこから流れ出る大仏次郎氏好みの詩情はやがて次代の新しい歌舞伎に一つの財産を与えそうだが、ただ今度の信康にしても家康にしても、自分の感情を洗いざらい自分のセリフにして説明してゆく手法のみを疑問とする。 梅幸の「鏡獅子」は肥満したせいか、手首ばかりで一向に全身的な躍動がない。松緑の「魚屋宗五郎」もこの人の六代目模写では一番習作の感じが抜け切れてない。やはり技巧としてのむずかしさなのであろう。(山口広一) |
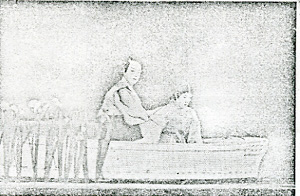 今月の菊五郎劇団は古い時代物狂言と黙阿弥狂言、それに新しい大仏次郎氏の創作劇を合せて新旧ともに広い範囲の努力を世に問うている。
今月の菊五郎劇団は古い時代物狂言と黙阿弥狂言、それに新しい大仏次郎氏の創作劇を合せて新旧ともに広い範囲の努力を世に問うている。