|
===けんらんの大舞台 顔見世=== 目新しいのに「女暫」 貫録示す猿之助の弁慶 冨田泰彦
第一は吉井勇作、舞踊劇「歌舞伎草紙」一幕、今年は不思議と阿国が題材に上らされる、富十郎の阿国、仁左衛門の山三を中心で樋口富麻呂画伯美術考証による花やかさ、第二は「吉野川」これは寿三郎、時蔵と共に鴈治郎、扇雀父子で花の吉野に花を添える、丸本劇中でもコクのあるものであることは「妹背山婦女庭訓」と芸題を据えてある点からみても、この一編の戯曲中でも重要な場である、第三は歌舞伎十八番「勧進帳」である、顔見世と「勧進帳」とは付き物のように、しばしば出ている、猿之助の弁慶は当代貫録において第一であり、南座でも再演と思う、富樫に寿海が出て例の「山伏問答」で名調子が聞かれ、義経の鴈治郎は先代以来「花」を添えるもの、寸こそ小さいが、能楽の子方を思えば却つで効果的だ × × 第四は「雪暮夜入谷畦道」を二八そば屋と大口の寮の二場、寿海の直次郎は先代羽左亡き後はこの優のもの、三千歳の富十郎とともに訥子の丈賀、簑助の丑など役ぞろい、最近志摩大掾という仰々しい名を鷹司家からもらつた清元志寿太夫が、持前の美声のみでかんじんの「芸」は鳶にさらわれて行かぬように祈る、第五は簑助と延二郎のコンビで「竜虎」を出す、今度は仮花道を「吉野川」から拝借して新しい振を見せるとか × × 夜の部の「女暫」は珍中の珍、いうまでもなく歌舞伎十八番の「暫」を女形で行く目新しいもので当代の立女形時蔵が貫録を示すもの、過去では、先代歌右衛門と先代梅幸とが上演したきりのもの、古典歌舞伎のおゝまかで花やかな大舞台にも所狭しと居並ぶ四人の腹だしや十人の女奴に至るまで数十人の登場人物の色彩美はまことに夢幻的である、また花道で愛嬌を添える重要な後見には鴈治郎が出、「受け」は仁左衛門、鯰坊主は簑助等いつもは鎌倉権五郎など役名がつくが、ここでば巴御前として優美なうちにも活気と洒落な処がいかにも「根元歌舞伎」を草書にしたようなもの、男では大勢の首を切るが、ここでは女奴との引ッ張りの見得などしその穴をゆくもの、歳末の馘首沙汰に遠慮したわけでもない、さらに花道の引込みも六法を巧みに逃げて、しかも、その味を示し、詮議の倶利加羅丸の宝刀が手に入つた喜びを表現して役名の巴御前も「播磨屋のねえさん」らしい、理屈ぬきの一幕に舞台と観客席とが相和する × × その「慶喜命乞」「盛綱陣屋」「雨の五郎」「夕顔棚」と盛り沢山な極め付狂言の後に成駒屋父子が東京で大好評を博した「曽根崎心中」が出る、今年は近松の三百年祭に当るための記念上演、こう端折って書いても紙数がつき詳しくは一見の上で・・・ |
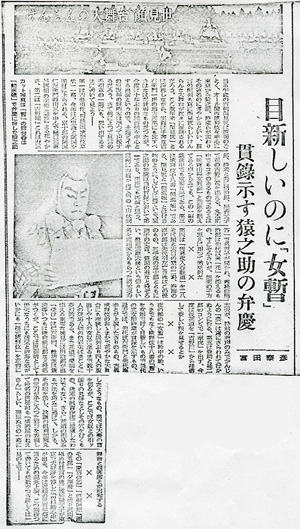 当る午歳の吉例顔見世は既報のごとく、オール関西歌舞伎を中心に東京から猿之助、時蔵らが加わりその連名のにぎやかさといい、狂言の配列も真に顔見世らしいけんらんな大舞台が次々に展開されるだろう、ここ数年来「顔見世」とは誇称しながら、実質は手薄な吉右衛門一座の地方巡業にも比すべきはなはだ貧弱なものだつたが、今度は十年ぶりの関西側を中心とする出演というので、土地ビイキの京阪神の好劇家は挙って声援するだろう、さて例によつて狂言の手引草の一端にも、思い出ずるままに書いて見よう――
当る午歳の吉例顔見世は既報のごとく、オール関西歌舞伎を中心に東京から猿之助、時蔵らが加わりその連名のにぎやかさといい、狂言の配列も真に顔見世らしいけんらんな大舞台が次々に展開されるだろう、ここ数年来「顔見世」とは誇称しながら、実質は手薄な吉右衛門一座の地方巡業にも比すべきはなはだ貧弱なものだつたが、今度は十年ぶりの関西側を中心とする出演というので、土地ビイキの京阪神の好劇家は挙って声援するだろう、さて例によつて狂言の手引草の一端にも、思い出ずるままに書いて見よう――