|
===劇信=== 三升の解脱は無難 進歩示す梅幸の鏡獅子 大鋸時生
[こ]の公演がつまらないというのではなく、せっかく劇聖団十郎といい口上場までつけるなら、客引きの歌文句に終わらせず、市川直系の役者や吉右衛門のように団十郎の芸統を伝える面々をあつめて、団十郎をケン称すべきでした。 [そ]れでこそ「劇聖」に報いる道だったと思います。 ◆・・・・・〇・・・・・◆ [さ]て「大徳寺」は団十郎の話術の妙を偲ばせる芝居で、演者の科白の巧拙がこの一幕の活殺を握っています。それに金ピカの大舞台、目白押しの役者群が構成するボリュームも必須の条件です。今度の久しぶりの上演は大たいこれらの条件をほぼ満たしたと思います。松緑(柴田)・彦三郎(佐久間)市蔵(滝川)ら敵役がとくに手揃いでした。海老蔵の秀吉は衣冠束帯の凛々しさは打ってつけですが、流れるような弁舌とはいいかねるのは案外でした。それでもその貫録のあがったことは確かです。話題の海老蔵の子、夏雄(三宝師)の初舞台はその度胸のよさに感心しました。どう育つか新しい楽しみです。 、◆・・・・・◇・・・・・◆ 「[解]脱」は三升が復活した十八番もののうちで、好い方のものだとします。三升の衰えが幽冥の国から来た景清に似合ったのも一得でした。ただし荒事の面白さは望むべくなく海老蔵の小四郎、松緑の文覚らのかっきりした演技にたすけられ無難というにとどまります。 ◆・・・・・◇・・・・・◆ [つ]いで六代目の影響下にある芝居となります。 [ま]ず梅幸の「鏡獅子」ですが廿五年六月(新橋演舞場)の初演が、たどたどしかったのに比べては大きな進歩が判り、 前シテに優雅さが出たのなど好もしいところです。 [し]かし六代目のイキが正しくつがれているかどうかはかなり問題でしょう。もち論、扇の扱いの悪くないのや後シテの毛頭をふる気構えに毛先にまで神経が通っていた、菊五郎の名品と比較しようというのではありませんが、梅幸としては、もっと厳しく「鏡獅子」に対決すべきではありますまいか。 [松]緑の「素襖落」にも、ほぼ同様のことがいえます。廿六年六月の新橋演舞場所演に比べてさえも崩れが目立ちます。太郎冠者が酒に酔いかもしだす可笑味が、時にはアチャラカめくからです。 ◆・・・・・◇・・・・・◆ [左]団次の「吉田屋」は菊五郎とちがって常磐津によっていますが、大たいは菊五郎的行き方で「総身が金」などの大切なセリフはカットします。そのくせ三味線をひいたり、茶の天目台を鼓に見立てたりする菊五郎らしい案は見逃しています。「ハナに扇の」や「仲直りすりや」のあたりに左団次独特の和事味を出したほかは、どちらかといえば中途半端な伊左衛門で、むしろ初役の梅幸の夕霧の容姿の美しさに目を見はります。 [し]かし松緑の「魚屋宗五郎」は廿三年八月の新橋演舞場所演に比べ松緑が自分を出そうとしている点に興味を持ちました。浦戸邸の玄関先で菊五郎がカットしていた「ままよ三度笠」の都々逸を唄うなどにそうした意気込みを見ました。だんだん酔っばらって行く段取りも酒の香りがプンプン匂うようだった六代目には遠いのですが。翫右衛門の技巧一点ばりの見てくれよりは松緑の未完成をとりたいと思います。ほかでは梅幸の女房、福助の召使おなぎ、照蔵の典蔵、菊十郎、新七の足軽がよい出来でした。 [大]仏次郎の「築山殿始末」は劇の展開が不十分で秀作とはいえませんが、松緑の家康、海老蔵の信康が大出来で、江崎孝坪の装置の好調と相まって見られました、中でも蓮池の場が素晴らしく明るい陽ざしの下で「静かなことはどうだ」と信康が独白するあたり詩があり最近の快さを味わいました。この場だけで十分に満足しました。九朗右衛門(服部半蔵)がぐつと調子を直したことにも好意がもてます。 [左]団次(築山御前)梅幸(徳姫)らが十分に描けておらず演技も不熟なのが、この芝居に大きくマイナスし、信康が太鼓を乱打する場につくりもののクライマックスを設定したのは破調といえましよう。なおここの踊りの列で本当にうれしそうに踊っている役者(ヒヨットコをかつぐ我勇の五、六人前方で)は名は知りませんが一際、目立ちます。(十六日目所見)=写真は右市川三升(景清)右市川海老蔵(江間小四郎) |
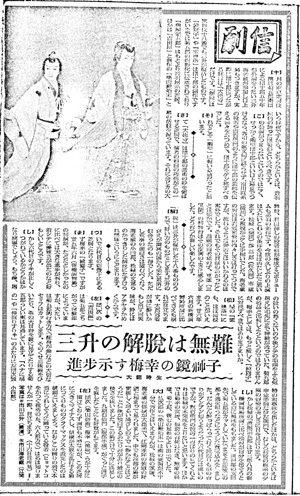 [十]月の東京歌舞伎座は菊五郎劇団による団十郎五十年祭公演をうたい三升、海老蔵が参加し口上場もつきますが、実際に団十郎につながる狂言は「大徳寺」だけです。「解脱」は歌舞伎十八番でも三升が復活したものです。「鏡獅子」や「素襖落」は団十郎の創作ですがいまでは菊五郎の影響化に伝承されており「魚屋宗五郎」はもとより音羽屋系の芝居、ほかは「吉田屋」と新作の「築山殿姶末」という昼夜ですから、どちらかといえば、音羽屋色の勝った団菊祭というべきです。
[十]月の東京歌舞伎座は菊五郎劇団による団十郎五十年祭公演をうたい三升、海老蔵が参加し口上場もつきますが、実際に団十郎につながる狂言は「大徳寺」だけです。「解脱」は歌舞伎十八番でも三升が復活したものです。「鏡獅子」や「素襖落」は団十郎の創作ですがいまでは菊五郎の影響化に伝承されており「魚屋宗五郎」はもとより音羽屋系の芝居、ほかは「吉田屋」と新作の「築山殿姶末」という昼夜ですから、どちらかといえば、音羽屋色の勝った団菊祭というべきです。