|
====劇評 旧作に前進あり 歌舞伎座の新国劇====
今月の新国劇ではこの作品が唯一の新作だし、かなりの冒険を承知のうえでの上演だし、さらに島田の阿Qが克明に計算した演技でよくやっているのも認めたいのだが、前述のような脚色のアマ味が原作の精神を十分伝え得なかった点で、これは宝クジの抽せんではないが、残念賞というところへ落ちついたようだ。 長谷川伸の「荒木又右衛門」では辰巳の荒木に、野村の桜井甚左衛門を配し、島田を河合又五郎へまわした。この配役は島田が甚左衛門だったかつての配役よりもはるかに妥当で、その島田の又五郎、野村の甚左衛門が佳良だ。 この作品は前半が理詰めで、それが少々ばかりモタつくけれども大詰の仇討がよくかけている。討つ側の荒木と数馬も討たれる側の又五郎と甚左衛門も、ともに武士道の冷たい義理の苦もんなのである。その武士道の悲劇をこの大詰の一場がよくとらえている。演出的に見ても仇討のあとの荒木のほのかな哀愁と空虚さをアラレの音に象徴させているなど心にくいまでの技巧である。 ただこの場での辰巳の又右衛門がそうした作意の深さにまで達しているかどうか。辰巳という役者は非常に感覚的な鋭さを持っている人だが、内面的な掘り下げ方が時おり飛躍してしまう人だからである。 真山青果の「荒川の佐吉」は子供をカセに使った博徒仲間の人情で泣かせる。この作者としては珍らしく理屈抜きの人情芝居である。演技評ではワキ役ながら野村の相模屋政五郎に風格があって優秀だ。「阿Q正伝」での呂と呼ばれる性格破産者「荒木又右衛門」での前記の桜井甚左衛門、それにこの政五郎親分いずれもあの淡彩的な芸格のよさが得がたい。 島田の荒川の佐吉も阿Q、又五郎に続いてこれもそろって悪くない。近ごろの島田は演技の□囗囗次第に抜けてきた。年齢□囗囗もあるだろうがこの人の円囗囗囗思わせるものがある。 このほか「王将」の第一編が再演されている。主題のつかみ方、筋の運びのムダのなさ、奇智とユーモアのある演出と、相変らずこの作品は北条秀司の代表作であることをうなずかせる。それに辰巳の坂田三吉も初演より整っていて、これも演技としての辰巳の代表作になりそうだ。 要するに今月の新国劇では「阿Q正伝」が新作であるほかは三篇とも旧作本位なのだが、その三篇の旧作にいずれも前進のあることが芝居を面白くしているのである。(山口広一)=写真は「王将」の一場面、右から辰巳の坂田三吉、外崎の小春、香川のお玉 |
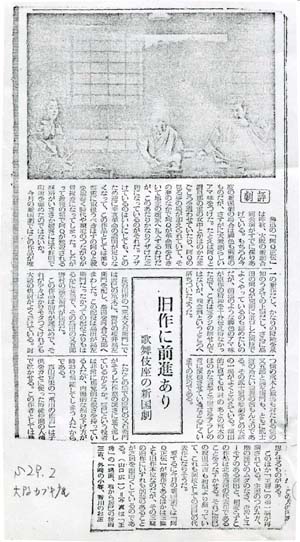 魯迅の「阿Q正伝」は昨秋、大阪の新劇合同公演がすでに採りあげている。もちろん今度の新国劇の場合は脚色も別種のものだが、さすがに大衆劇らしいアマ味をつけた。たとえば阿Qと趙旦那の家の女中とがほのかな恋ごころを通わせていたり、阿Qの見る夢の場が加えられていて、その夢のなかで阿Qが革命軍をひきいて地主の趙家へ乱入するわけだが、このあたりかなりフザけた芝居になっているのがそれだ。フザけているのはいいにしても、このため逆に辛亥革命の説明が足りなくなって、この作品としては最も慎重に取扱うべきはずの阿Qと彼を取巻く時代や環境のつながりが骨抜きになってしまった。したがって最後の幕で阿Qが銃殺される経路がいささか観客には不鮮明で印象を弱めたのではないか。
魯迅の「阿Q正伝」は昨秋、大阪の新劇合同公演がすでに採りあげている。もちろん今度の新国劇の場合は脚色も別種のものだが、さすがに大衆劇らしいアマ味をつけた。たとえば阿Qと趙旦那の家の女中とがほのかな恋ごころを通わせていたり、阿Qの見る夢の場が加えられていて、その夢のなかで阿Qが革命軍をひきいて地主の趙家へ乱入するわけだが、このあたりかなりフザけた芝居になっているのがそれだ。フザけているのはいいにしても、このため逆に辛亥革命の説明が足りなくなって、この作品としては最も慎重に取扱うべきはずの阿Qと彼を取巻く時代や環境のつながりが骨抜きになってしまった。したがって最後の幕で阿Qが銃殺される経路がいささか観客には不鮮明で印象を弱めたのではないか。