|
もちろん、京の顔見世の伝統からすれば、今年のような大阪側の俳優に主体性のある座組みのほうが本当なのに違いないが、それよりも、今年の顔見世では、むしろ上演狂言の配列とその配役の企画に勝算があったようだ。 たとえば、昼の部では「妹背山」における均整のとれた配役の成功がこれにあたる。時蔵の定高を中心に寿三郎の大判事、鴈治郎の久我之助、扇雀の雛鳥と顔をそろえた配役が近ごろでの安定感だったのである。 時蔵の定高はこの人の世話味がかった腰のひねりようや肩の落し方が、時おり気品を低めるキズはあるが、風格よりも情味の定高としては、今日での第一級品である。寿三郎の大判事は相変らずセリフの描線が弱い。それだけに仮花道での「同じこの世にわいた虫」とか、後段での「読みさしの無量品」あたりのキメ手が受け切れてないが、役者の柄としては時蔵の定高に対立する大判事であろう。鴈治郎の久我之助は哀愁の描き方に洗練が加わってきているのが佳良。これらの先輩に伍して扇雀の雛鳥が、これも一種不思議に新鮮なツヤを発散させている。個別的な成績を超えて、いずれも均衡のとれた配役の成功である。
「雪暮夜入谷畦道」という芝居は依然として序幕の「そばや」に生命がある。雪の夜の哀感をこれほどに美化してみせるのは、さすがに黙阿弥の詩だからである。 寿海の直次郎は丑松とのやりとりのあいだに、この役での全体的な円熟さが示されている。訥子の丈賀は手ざわりの堅さを別にすれば、この人なりのうま味はある。 「大口の寮」では志寿太夫を聞くべく、富十郎の三千歳には黙阿弥好みの情艶がない。 × × × 夜の部ではまず時蔵の「女暫」が企画の成功である。極彩色のパステルで塗りたくったようなこれは歌舞伎の自由画である。仁左衛門のウケはとにかくとして、なまず坊主の枯れたシャレッ気が延二郎では無理だし、吉三郎以下の腹出しも欲をいえばもっとハメをはずした面白さでなくてはいけないのだが、それらの不満があるにしても時蔵の女暫が意気もよく色気もあり、立派にこの上演の意義をつなぎとめたのをほめたい。 「盛綱陣屋」はこれも昼夜を通じての顔ぞろいだが、そのわりに演技に集約されたものを感じさせなかったのは、仁左衛門の和田兵衛、富十郎の篝火、猿之助の信楽太郎あたりの線に破調があったからではあるまいか。いずれにしても寿海の盛綱は注進受けの颯爽たる風姿が第一であり、鴈治郎の微妙とともに点をかせいでいる。 さらに夜の部では近松の「曽根崎心中」が案外の成績で、まさに今年の顔見世の有終の美を発揮していたのを特筆しておきたい。 この成功の第一は宇野信夫の脚色がこれまでの近松物の盲点を衝いているからだ。いいかえれば従来の類型を避けて近松のリアリズムに徹しようとした作意なのである。成功の第二はお初にふんした扇雀のめざましい進境である。特に「天満屋」の場で床下に徳兵衛を隠した一人芝居のあたり、芸格の新鮮さといい、神経の行きとどいた表現力といい、ある意味では今年の顔見世をくるめて第一の傑作とさえいえる。 脚色よし、演出よし、それに前述の扇雀の新しい魅力を加えて「曽根崎心中」は昼の部の「妹背山」とならんで今年でのよき記録となった。 真山青果の「慶喜命乞」は今さら演ずべき狂言でなく、見るべき狂言でもない。一体、真山青果の作品を一貫している皇道派的精神主義は早急に追放すべきである。 東京で好評だったと聞いた「夕顔棚」も、猿之助のお婆さんがスッカリ曽我廼家五郎であり、その不潔な感じはまるで色情狂的新舞踊である。愚劣すぎる。 × × × 以上、二つや三つの不満を勘定に入れるにしても、今年の顔見世は前記したとおり上演狂言の配列と配役の妥当さで見るべき佳作があった。さらにこれを俳優の個別的な成績表に仕立てると、扇雀、時蔵、寿海、鴈治郎という打撃順になりそうだが、第一打者に新進の扇雀をすえたのは必ずしも筆者のみの過大評価でもなさそうだ。(山口広一) (写真)「曽根崎心中」=鴈治郎の徳兵衛(左)と扇雀のお初 (写真)「女暫」=時蔵の巴御前(左) |
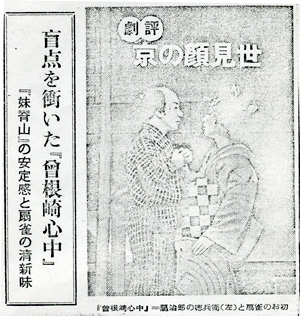 近年の顔見世(京都南座)はほとんど東京側の俳優ばかりの出演だった。それが今年は大阪側の俳優が文字通り総出演して舞台のイニシアティブをとった。戦後といわず、おそらくこれは十数年ぶりのことだと思う。
近年の顔見世(京都南座)はほとんど東京側の俳優ばかりの出演だった。それが今年は大阪側の俳優が文字通り総出演して舞台のイニシアティブをとった。戦後といわず、おそらくこれは十数年ぶりのことだと思う。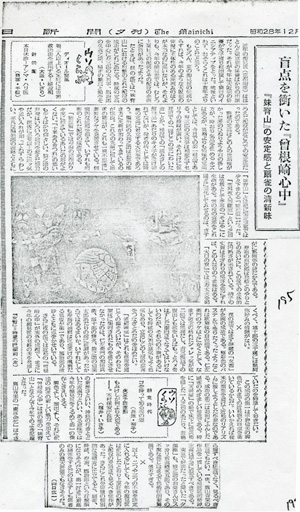 「勧進帳」では寿海の富樫がワキ座に控えているあいだの形がよくない。「士卒をひきつれ」の愁いも小々ばかり仰々しい。猿之助の弁慶はいろいろ趣向を変えた努力だが、総体に必要以上の芝居ッ気や思い入れが却ってわずらわしい。平凡な鴈治郎の義経とともに「妹背山」とは逆に集計点数では少々下まわる「勧進帳」だった。
「勧進帳」では寿海の富樫がワキ座に控えているあいだの形がよくない。「士卒をひきつれ」の愁いも小々ばかり仰々しい。猿之助の弁慶はいろいろ趣向を変えた努力だが、総体に必要以上の芝居ッ気や思い入れが却ってわずらわしい。平凡な鴈治郎の義経とともに「妹背山」とは逆に集計点数では少々下まわる「勧進帳」だった。