|
====三月の芝居展望 新作の競演で賑わう==== ――「絵島生島」早くも話題に――
[歌舞伎座] 本紙に連載中の「絵島生島」が作者船橋聖一自身の脚色で劇化上演されるのが早くも話題になり配役懸賞募集に応募の葉書が毎日平均三千通も劇場に殺到するので係りが悲鳴をあげている、今回は月光院(左団次、以下配役は全部予想による)と間部越前守(彦三郎)のラブシーンから始まり、越前守が愛情の証に指を切るといい出したことから、指を切る役者の所作を見たいと、月光院がお気に入りの奥女中大年寄の絵島(梅幸)と奥医師好竹院(鯉三郎)に命じ、禁制を破って人気役者の生島新五郎(海老蔵)と二代目団十郎(松緑)をひそかに千代田城内大奥へ呼び寄せることになる、生島は芝居見物にきた絵島の美ぼうに心をひかれ、団十郎の留めるのも振切り、菓子箱に忍んで大奥へ行く、ところが反月光院派の女スパイ宮路(権三郎)の訴えで危く局改めで捕われそうになるが、月光院に救われて、絵島の部屋で二人の男女が抱擁するところで第一編の終りになつている 福助が吉原の安女郎に落ちぶれた身を恥じて自害するお染にふんし、劇中劇に本舞台を花道に見たて「助六」の花道の出端だけを松緑の団十郎の助六で、初演当事の荒事の古劇味を復活させて見せる、たゞし記録によると尺八を振上げて男達を追っかけながら橋がかりから出るだけだったそうだが、あつけないので和事味を加えてやや洗練されたやり方に変え、柑子色の木綿のハチ巻に黒小ソデの正徳衣装で河東節連中の半太夫節を入れるのが珍しい 次も新作で能狂言から輸入の「唐相撲(とうすもう)」で日本人の力士(松緑)が祖国へ帰りたい一心から唐の皇帝(左団次)の命令通りに唐人たちと取組み、片つぱしから投げ飛ばすというお笑い舞踊劇、最後が「みそかに月の出るさとも・・・」の名ゼリフで知られた「御所五郎蔵」で、海老蔵の五郎蔵のために前田青邨画伯が衣装に風神雷神を新たに描く、土右衛門は松緑、皐月は梅幸、逢州は福助 順序が逆になつたが昼の部は、桃の節句を祝つておヒナさまが夜中に白酒に酔って踊りだす若手の「雛の夜祭」から始まり、新作の「笛吹童子」は、去年一年間NHKから放送されて全国の児童に人気のあつた連続放送劇から作者北村寿夫が脚色した音楽劇、応仁の乱の直後に野武士玄番(市蔵)らに城を奪われた城主の子の双生児の兄弟の波らんの多い物語で兄の荻丸と弟の菊丸に兄弟の梅幸と九朗右衛門がふんし、忠臣右門父娘を左団次と福助、隼人を松緑、霧の小次郎を彦三郎、最後に梅幸の二役の胡蝶尼が釣橋を切られて落ちるところは、ケガをしないよう下にハンモックをつるはず、この狂言に限り学童は半額の丗円で優先的に幕見ができる 続いて松緑の「義経腰越状」だがいつもの五斗三番のあとの鉄砲場で、海老蔵が空鉄砲をうつ泉三郎を附き合う、あとが梅幸、、海老蔵の「十六夜清心」で白蓮は彦三郎、求女に由次郎が抜てきされる (写真(上)は歌舞伎座の「十六夜清心」海老蔵の清心に梅幸の十六夜(下)は明治座の「白野弁十郎」島田の白野に香川桂子の千種姫 ――関西歌舞伎の東上―― [帝劇] 帝劇出演は、猿之助と段四郎が日華事変の最中以来、中車が戦後初めて、時蔵が終戦の翌年以来、関西から仁左衛門、簑助、鶴之助に東京初出演の延二郎も加わり、附人を入れて総勢丗名が今回は楽屋に泊らずに旅館泊り、早替りの狂言が三つある、昼は「累物語」で時蔵が累、高尾太夫の亡霊、腰元梅ケ枝の三役「龍虎」で簑助と延二郎が龍虎からモチ売りに変り夜は「大文字屋」で仁左衛門が老け役の萬屋助右衛門と悪番頭権八の二役、その中の「累物語」は三年前の歌舞伎座の時と同様仁左が与右衛門をやるが、身売りの前に累に見染められる豆腐屋を珍しく復活させる、土橋では幕切れの世話だんまりの狂言半ばに延二郎の初お目見得の口上がある、九年ぶりの青果作「人斬り以蔵」では、兄の以蔵(猿之助)に毒酒を飲ませ自分も死ぬ可れんな娘百世にふんして鶴之助が女形をやる、最後は中車と段四郎の「勢獅子」 夜の部は林房雄初の劇作「島の西郷隆盛」という奄美大島に流罪の若き日の西郷を描く新作で猿之助の主演、次が簑助、延二郎、鶴之助の新作舞踊「凧絵競べ」と猿之助の五郎、時蔵の小林の舞鶴で「草摺引」最後の「大文字屋」は片岡十二集の一つ亡父の当り役を仁左がどんなふうにやりこなすかが見もの、ここでも鶴之助が女形で妹のお松をやり遊女揚巻(芦燕)と駆け落ちした道楽者の夫の助六(延二郎)のために、お松が身を売って揚巻を見受けしようとしたり、それを知って父助右衛門が身代金を投げ出したりして、徳川封建期の義理人情の世界を色濃く描く上方歌舞伎 ――新国劇の記念公演―― [明治座] 新国劇が座長沢田正二郎の没後に更生してから廿五周年の記念公演で昼は沢正没後の当り狂言「王将」(北条秀司作)を六年ぶりに再演これは将棋の関西名人といわれながら不遇に終った奇人坂田三吉の後半生を描いた三部作の第一部で再び辰巳の三吉の好演が期待される、次が廿五周年を祝つて長谷川伸が島田のために書き下した「酒ツ乞食」で、初めは、“兼子市之丞命の恋”という題だったのを改題したもの、天保六花選の金子市之丞と字も違うが、人間も風采があがらず料理屋などから酒ばかりもらって歩くので酒ツ乞食と呼ばれる男になつている、その市之丞と一ぜんめし屋の娘(香川)とのロマンスに、彼を仇とねらう若侍や旗本、盗賊をからませてチャンバラもあり、辰巳が河内山で助演する 夜の部は、沢正生前からの当り狂言「白野弁十郎」で、通し上演は戦後初めて、島田の白野、辰巳の隊長、香川の千種姫、宮本の栗栖、あとに北条秀司の新作現代劇「早春」がつく、これは同じ題名の放送劇と井上正夫にはめて未上演に終った“手風琴”とをまぜて書き直したもので瀬戸内海に面した港で、娘を探して旅を続けるお遍路さんの手風琴ひきの老人(辰巳)と偶然知り合つた戦災孤児の娘との愛情を描いている |
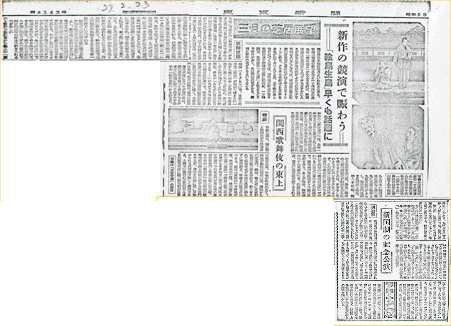 興行界の冬枯れの月といわれる二月も、新橋演舞場の新派合同と一ツ橋講堂の民芸の「煉瓦女工」が大入りを続け、歌舞伎座は延長興行に入ってからさすがに入りが落ちたが夜の部がよかつたおかげで平均七八%にこぎつけ、明治座の菊五郎劇団は反対に昼の部が強く辛うじてトントンに終り、どうやら各劇場とも赤字をまぬがれてホツとひと息、さて春のあし音が近づく三月は、演舞場の新派が堂々延続のほか歌舞伎二座に新国劇、−ツ橋講堂、文学座の「どん底」と色とりどりで新作が多く、外は汚職の花ざかり、劇場は新作の花ざかりというところ
興行界の冬枯れの月といわれる二月も、新橋演舞場の新派合同と一ツ橋講堂の民芸の「煉瓦女工」が大入りを続け、歌舞伎座は延長興行に入ってからさすがに入りが落ちたが夜の部がよかつたおかげで平均七八%にこぎつけ、明治座の菊五郎劇団は反対に昼の部が強く辛うじてトントンに終り、どうやら各劇場とも赤字をまぬがれてホツとひと息、さて春のあし音が近づく三月は、演舞場の新派が堂々延続のほか歌舞伎二座に新国劇、−ツ橋講堂、文学座の「どん底」と色とりどりで新作が多く、外は汚職の花ざかり、劇場は新作の花ざかりというところ