|
(明治座 梅幸)
今月の明治座で尾上梅幸は、昼夜合せて六役のうち「元禄忠臣蔵」の大石内蔵助妻おりく「絵本太功記」十段目の十次郎「明烏夢泡雪」の浦里「質庫魂入替」の八重垣姫などと初役が多く、ことに暮に「賀の祝」の桜丸で好評を博した梅幸が再び十次郎を好演して話題となつている、そこで明治座の楽屋に梅幸を訪ねて十次郎を中心に持役の芸談をきく(写真は梅幸の十次郎) 「四つの初役に奮闘 役の苦心を語る梅幸」 「ボクは今まで初菊ばかりで、このあいだ死んだ市村のにいさん(羽左衛門)の十次郎で花形歌舞伎以来三回ぐらいやりましたし、親父さん(六代目)の十次郎でやった一番最後は、新橋演舞場の開場式の時でした、ですから無論親父さんのも見ていますが、今度初役で十次郎をやるについて、改めて親父さんのもよく知っている菊十郎に聞いてやつています、衣裳も親父さんの通り赤にしていますが、ノレン口から出てきたところから、“母さま・・・”とのあいだなんか、やつぱりむずかしいですね、とにかく若い少年というか若武者だから、そういうところが出なきやいけないし、このあいだある人にいわれちやったんですよ、“品がよすぎて敦盛みたいだから、もつとサムライにならなきやいけない"ってね・・・どうしても形が敦盛に似てますからね 賀の祝の桜丸もやつばりノレン口から出るんですが、桜丸は舎人であり切腹する覚悟で出てくる、だけど十次郎のほうは戦地へ行くんで、少年飛行兵みたいに勇んでゆくんですからね、物語でもケガにとらわれてグニャグニャしてはい けないでしようね、この物語りのあいだなんか、親父さんはよかったですね、形がきまるようなきまらないようにやつて・・・それに親父さんはあのころすでに身体がわるくなつてきたのにあの年で若く見えたし、引っ込みもよかった・・・」 「明烏」では、左団次の時次郎は先年三越劇場で時蔵の浦里でやつて以来二度目だが、梅幸は、浦里が初役ばかりでなく、だれのも見ていない「ボクが三つぐらいの年に、親父さんの時次郎、播磨屋のおじさん(吉右衛門)のおかやで、先代の菊次郎さんが浦里をされたんですが、全然おぼえていません、ことにその後はうちのほうで出ないし、左団次さんが三越でやったときも、ほかへ出ていて見られませんでした、そこで赤坂のおじさん(先代梅幸)のを梅朝さんに聞いてやってますが、結局責めで子供がむずかしい役だから、子役さんがしっかりやってくれないとやりにくい役ですね、ボクとしては先月三千歳をやって、また今月同じようななりだし、前のクドキも同じようなので、気が変わらないんだけど・・・」 もう一つの初役は「質屋の蔵」の八重垣姫だがこれは初役といっても軽いお笑いの舞踊劇で、これといった仕どころもないが、梅幸にとっては一応思い出のなつかしい出し物だ 「何しろこの前にやったのが、ボクが十五歳で丑之助のころで、歌舞伎座の大喜刹に、若手も若手十代の連中ばかりで出したんです、ボクはその時は虎蔵で、今の歌右衛門さんが児太郎時代で八重垣姫をやり、松緑さんは豊といつていたころで今度と同じ雷神でしたが、松緑さんがそのころはやったチャールストンを舞台で踊ったのをおぼえています」 「男女道成寺」は六代目の死んだ年に京都南座の顔見世で松緑とやつて以来で、東京では初めて、「京都の時は後ジテがあつたもんだから、向うが入つちやつたあとで山ずくしをボクがズーツとやっていましたが、今度は後ジテがありません」 最後に「一本刀土俵人」のお蔦について・・・ 「お蔦は、前に演舞場でやつてから二度目ですが、我孫子屋のところよりあとのお蔦の家のほうが、水商売上がりという前身を見せなきやいけないので、むずかしいですね、旅館の番頭さんなんかに聞くと“素人か水商売の女か見分けるのは階段の上り方でわかる、素人はモタモタ上ってゆくし、水商売の人は軽くポンポンと上つてゆく”といいます、喜多村緑郎さんがうちの親父の茂兵衛でお蔦をおやりになつた時もそうでしたが、ボクも段を上る時にそれを見せています、我孫子屋の衣裳も、この前は薄い茶系統でしたが、今度はお納戸にネズミのシマを入れています、イキになつちやあいけないんでね とにかく、お蔦は酔っぱらっていて、大して茂兵衛を気に留めていなかつたのが、あんまり茂兵衛がうれしそうに花道を入ってゆくので、そんなにうれしいのかなあと、ジーツと見てうしろ姿が印象に残る、ですからあとの“思い出した”も茂兵衛のうしろ姿を見てやつと思い出すようにしてやっています」 |
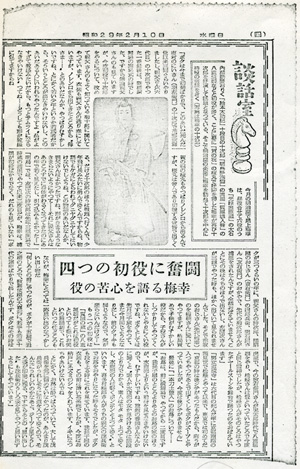 ====[談話室]====
====[談話室]====