|
====僕の「地獄変」 三島由紀夫==== 歌舞伎は子供の頃から好きだが・・・
私は子供のときから歌舞伎が好きで、ことに丸本物が好きで中学から高等学校時代には、丸本をもって行って、役者の型を舞台を見つめながら鉛筆だけうごかして、メモしたものであった。こういう年齢に夢中になったことは怖ろしいもので、今でも私がいちばん学をふりまわせるのは、歌舞伎に関してである。 役者では先代宗十郎がおひいきで、皆がけなすからますます好きになり、おしまいにはあの悪声までが、よくてたまらなくなった。あのねばる演技と大々的(?)なマスクが丸本物を演ずるには必須な条件であるということもわかって来た。一つおじぎをするにも大仰に段取をつけるあの手つきの一つ一つが浄瑠璃の奇怪な文章をいかに体現していたことよ! 私は現代語や中途半端の新歌舞伎調セリフの新作がきらいであって、自分では、いつか形式もセリフもことごとく歌舞伎に則った新作を書きたいものだと思っていた。「地獄変」の劇化の話は、渡りに船だった。 しかしやってみるとただ擬古文というだけでなく、浄瑠璃のあのグロテスクな素朴なユーモアをたたえた悪趣味きわまる文体の再現は、実にむずかしかった。観客や読者の立場では面白おかしいことが、作る立場に立つと面白いどころのさわぎではなかった。大体浄瑠璃作者の頭には日本や支那の古事に関する耳学問がいっぱい詰っていたが、浄瑠璃を書くのにじゃまになるような教養は一つもなかった。ところが我々は、文楽をきいた耳でハイフェッツをきき、帰りは酒場でサルトルを論ずるという理不尽な生活をしている。これで浄瑠璃を書こうというのは虫が好すぎる。自慢にもならないが、やっと脱稿して、歌舞伎座で本読みの最中に息がつづかず、脳貧血を起しかけた程である。 さて上演されてから、私は台本の計算違いに気づいた。元はといえば、この企画は獄門帖の大火の場面が成功したところから、大道具と効果に自信を得て、そこから企画が生れたものと思われる。事実、大道具の努 力と成功は目ざましく、大詰の車は見事に焼けすぎ、そばで見ると怖くなるくらいで、おかげで台本の大詰のセリフのあらかたは不要になってしまった。 しかし今もなつかしく思い出すのは、舞台げいこの当夜、銀座に大火事があって、芝居道の迷信にもあるとおり、一同がこの芝居は大当りをする。と希望的に語り合ったそのときの情景である。(作家)写真は「地獄変」の舞台 |
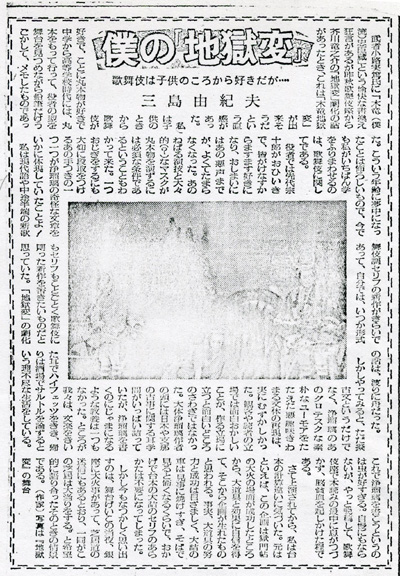 武者小路実篤氏に「木竜(僕流)忠臣蔵」という愉快な書換え狂言があるが昨秋歌舞伎座から芥川龍之介の「地獄変」劇化の話があったとき、これは「木竜地獄変」が出来そうだという直感があった、
武者小路実篤氏に「木竜(僕流)忠臣蔵」という愉快な書換え狂言があるが昨秋歌舞伎座から芥川龍之介の「地獄変」劇化の話があったとき、これは「木竜地獄変」が出来そうだという直感があった、