|
====新秋九月の芝居==== 各座前景気も好調 一斉に一日初日で開幕
―――華やかな口上 幸四郎の追善興行――― [歌舞伎座] 先代幸四郎の七回忌追善興行なので、今の幸四郎の自宅から故人の胸像を運んで劇場の廊下に飾り、昼の部の口上では明治座から海老蔵と松緑がかけつけて幸四郎と共に故人の遺児の兄弟三人がそろつて列ぶほか、関西から門弟としてただ一人加わる錦吾を入れて合計三十名、このうち病気で急に休演となつた吉右衛門の代りに三津五郎が皮切り猿之助、時蔵、三升ら廿人もしやべるので、一人一分ずつしやべつても廿分、そこで川尻清潭が特に台本を執筆、背景も大いにこつて、高麗屋の四ツ花菱の紋散らしの金ビヨーブをバックにした桃山風の書院の装置を新井勝利が引受け、口上に脚本を書き舞台装置があつてしかも廿分近くの長時間にわたるのはこれが初めて この興行に新しい引幕が二つ、一つは某化粧品会社から幸四郎へ贈られた花幕で追善狂言の「勧進帳」の前に引く、もう一つは囗囗囗の高麗蔵の襲名を祝う・・・・・・・・・から始まり新高麗蔵の牛若丸に三升が大天狗をつきあう、次が「忠臣蔵」九段目山科閑居の場で猿之助の加古川本蔵が見もの、戸無瀬は時蔵、小浪が松蔦、お石が宗十郎、力弥が高麗蔵で、由良之助は松竹京都の映画「忠臣蔵」で大石内蔵之助をやつている幸四郎 続いて「口上」があつてから「勧進帳」で、幸四郎の亡父譲りの弁慶に兄海老蔵の富樫、勘三郎の義経、最後が歌右衛門の所作事「隅田川」で舟長は勘三郎 夜の部は、吉の病休で中止した「二条城の清正」の代りに「滝口時頼」が出る、これは時頼が父の反対で横笛に失恋して仏道に入る話を描いた池田大伍の廿代のころの作で、大正三年に帝劇で猿之助と森律子が上演して以来の復活(その間東儀鉄笛らが有楽座で上演したことがある)今回は勘三郎の時頼に歌右衛門の横笛で“読む戯曲” といわれた単調を補うために、久保田万太郎がアレンジし、序幕に横笛が白拍子になつて踊る西八条桜の宴の場を新しく追加し、この場に長唄おはやし連中が顔にお化粧をして舞台に列ぶ、装置と衣装は渡伊する守屋多々志の置き土産 次に踊りが二つ「連獅子」では高麗蔵の襲名を祝って幸四郎が親獅子をつき合い、「四季三葉草」は勘三郎の三番、歌右衛門の千歳、三津五郎の翁、最後がときわ津の女師匠にふられて自殺したアンマのたたりで女師匠と情夫がのろい殺される怪談劇「蚊喰鳥」(宇野信夫作)で、五年前に東劇で猿之助が富十郎、仁左衛門と初演したもの、今回も猿之助がアンマの兄弟の辰の市と徳の市の二役をやり、女師匠は時蔵、情夫の遊人孝次郎は中車 ―――めずらしい二作 中山七里」「生きている小平次」 [明治座] 菊五郎劇団と海老蔵で、権十郎は健康すぐれず休演、昼の部は海老蔵が三年前に通しで出した「河内山」を松江邸から玄関先まで見せる、彦三郎の松江候、福助の浪路、左団次の高木小左衛門、鯉三郎の北村大膳 次が「戻橋」で、梅幸の小百合、彦三郎の綱、めずらしいのは六代目が度々上演した長谷川伸作「中山七里」を復活、六代目の最後の上演は昭和廿二年一月帝劇で花柳章太郎と初顔合せのときで 今回は松緑の川並の政吉、梅幸のおえんとおなかの二役、左団次の徳之助、彦三郎の文太郎といつた初役ぞろい、そこで川並の研究に松緑、市蔵、鯉三郎、権三郎たちが廿九日早朝から深川の木場へ見学に出かけた 夜の部は「妹背山」の御殿から始まり、梅幸の四年半ぶりのお三輪に松緑が鱶七、彦三郎が入鹿と豆腐買、福助の橘姫に海老蔵が求女をつき合う好配役 鈴木泉三郎作「生きている小平次」の復活もめずらしい、これも六代目が生前に松緑に上演を囗囗囗とがあり、いわば六代目囗囗囗もいうべき出し物 もっとも松緑が再三上囗囗囗したが、その都度劇場囗囗囗対され、今回やっと囗囗囗て実現に至ったもの、囗囗囗近をめぐる愛欲闘争の囗囗囗松緑、小平次を左団次囗囗囗 最後が海老蔵の「黒手組囗囗囗昭和廿三年一月に三越劇場囗囗囗した時も海老蔵が二役囗囗囗郎のくだりを「三枚目囗囗囗いから」ときらってカツ囗囗囗けあって、今後も敬遠囗囗囗狂言に変えるはずだつ囗囗囗再び権九郎のくだりを囗囗囗揚巻は福助、鳥居が彦囗囗囗が松緑 ―――オール新作の新派――― [新橋演舞場] 新派合同で四十日間興行、映画に出ていた小堀、藤村、喜章と目をわるくして四月から休んでいた赫子がそろつて久しぶりに出演するほか、女優をやめていた安部陽子が五年ぶりに復帰し、岩井半四郎と映画女優の高橋豊子、廿の扉の柴田囗囗囗(休演は映画に出てい囗囗囗ドを痛めたすみれの囗囗囗ール新作で、脚色物が囗囗囗連載小説の劇化が三つ囗囗囗説を脚色したのが二つ囗囗囗津柳浪の原作物が一つ囗囗囗 昼の部は・・・・・・・・・・・・・・ =====秋の花街おどり競演決る===== 秋を飾る花街舞踊は今年もまた各組合とも想を練って既に準備にとりかかっているが、早くも出し物の決定したものを挙げると、先ず新橋の東をどりは十一月一日から廿五日間、昼夜二部制の長期興行で 船橋聖一新作「瀧口入道と横笛」に川口松太郎作の芸妓もの(題未定)、他に八木隆一郎及び綺堂の原作もの、古典で常磐津「釣女」を上演 柳橋みどり会は明治座で十月廿七日から十一月一日までの六日間 小島二朔新作の「振袖流し」(清元梅太郎、常磐津文字兵衛作曲)田村西男作「椀久色神送り」それに「太刀盗人」「関三奴」「曽我菊」「浮世絵三題」 浅草の浅茅会は十一月廿六日から十二月一日までの六日間明治座で昼夜二部制 吉川英治原作、林悌三脚色の「吉野太夫」久保田万太郎作「都風流」古典で「宗清」「峠の万歳」「五人猩々」 などが内定、向島かもめ会は浅草スミダ劇場で十月末の二日間、田村西男作「夢の浦島」「大森彦七」「田舎源氏」「鶴亀」などがきまつている |
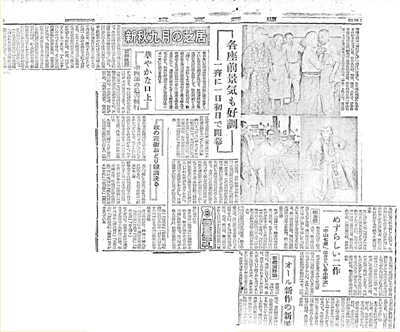 夏のあいだ映画撮影や地方巡業に出かせぎしていた東京の劇団が舞戻り、新橋演舞場と明治座の内部改修も完了して秋の観劇シーズン開く・・・その前しよう戦の九月興行は、歌舞伎座と明治座の歌舞伎合戦が人気を呼んで両劇場とも前売開始第一日に三階席を売り切るほどだし、演舞場の新派もオール新作で活気を呈し、前景気好調のうちに大劇場は明一日一せいに初日をあける
夏のあいだ映画撮影や地方巡業に出かせぎしていた東京の劇団が舞戻り、新橋演舞場と明治座の内部改修も完了して秋の観劇シーズン開く・・・その前しよう戦の九月興行は、歌舞伎座と明治座の歌舞伎合戦が人気を呼んで両劇場とも前売開始第一日に三階席を売り切るほどだし、演舞場の新派もオール新作で活気を呈し、前景気好調のうちに大劇場は明一日一せいに初日をあける