|
====大阪歌舞伎座ヒルの部・評==== 新派調抜けた「命美わし」 「逢坂の辻」カブキの形式美
「命美わし」四場は「懐古館」という自殺名物屋敷を中心としたもの、ある夜、父早吉(伊志井)と寛一(喜章)が若い未亡人あさ子(紅梅)を助けた、そして早吉はつづいて前市長の息子(島)にもてあそばれた教員房江(すみれ)を救助して来た、寛一はあさ子の自棄的な生き方に対して平手打でその愛情を示し、房江には次男修治(北尾)が清い恋心を抱きその挙句二人は逃避行する、母のみね(英)は心配のあまり倒れるが快雲(松宮)のはからいで一度に二組の幸福な夫婦が生れるという明るい大詰で幕になる「命美わし」の主人公は人生肯定派の早吉夫婦である、全体が文学座のようなふん囲気につつまれて新派調は少なく、伊志井が好演 「南地心中」のうち「逢坂の辻」一幕は泉鏡花原作を大幅に久保田万太郎が手を加えたもの、ひと口にいえば新派のカブキで、その形式美をたのしめばよい、芸者に囲まれての丸官(大矢)の花やかな花道の出、その妾お珊(章太郎)と手代多一(喜章)の仲をうたがって多一を侮辱する丸官など時代がかつたのを承知でみれば面白い「春琴物語」の佐吉の延長のような二枚目多一を喜章はイヤ味なくこなしている、章太郎のお珊もキレイだが、水谷八重子の穴をもった市川すみれの多一の許嫁お美津は力一杯の演技で「おみやげこうておくれやす」の声は哀調をもつて迫ってくる、ただし登場人物全部をひつくるめて語尾のハネ上った大阪ベンには参った 「花と龍」では点景的人物だつたドテラ婆さんの半生を画いた「女侠一代」は章太郎の汚れ役ということをヌキにして吉田磯吉(伊志井)に心をひかれて一生を台なしにした哀れな親分気質の女を章太郎はハッキリ浮び上らせている、発端の時代背景は明治二十四年で皆木組のドテラ婆さんことギンは二十五才の吉田にぞつこんほれこむ、このギンは鉄道の権利をとるためにその技師と肉体関係まで結んでいた、またその金のために気の弱い夫与一郎(大矢)は娘お幸(紅梅)を芸者に出した、しかし二年後、ギンは権利をとられたことを知り、西沢組へ殴り込みをかけるが、そこに吉田がいたために逃げかえり、味方は敗北となり小頭銀造(喜章)は足を斬られてもどる、そしてお幸と関係のあった吉田が満州行きのあいさつに来る、それを知つたギンは吉田のあとを追つて満州へ行く、その後若松一の親分となつた吉田は満州で失敗してうらぶれたギンを昔のドテラ婆さんにしてやる、ところがギンの次の夫幸次(伊井)はやくざで信用をおとして、とうとう国本一派をバラして警察行きになる、大詰の仲介にきたギンと吉田との対面は新派独特のペーソスをもつている、気の弱い前夫(大矢)が持味以上の演技で笑わせていた(東川) ====私の初舞台 オヤジの背中で 嵐璃珏==== 明治三十八年六月、嵐珏蔵という名で弁天座で初舞台をつとめました、オヤジ(先代璃珏)の背中に負われて出ました、狂言は「不如帰」です、浪子さんが先代芳三郎、武雄が十二代目仁左衛門でした、口上が名人といわれた団蔵さんがして下さいました、オヤジは百姓で卯三郎さんもご一緒でしたよ、ところで私の役は漁師の子供で、六つの時でした(関西歌舞伎) |
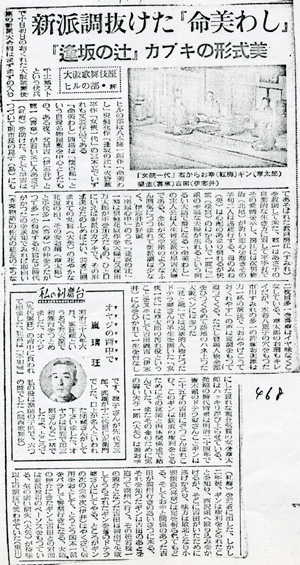 千土地ストという伏兵で十日初日のおくれた大阪歌舞伎座の新派大合同はまずまずの入り、ヒルの部は八木隆一郎作「命美わし」泉鏡花作「逢坂の辻」火野葦平作「女侠一代」の三本立でいずれも文芸作品である
千土地ストという伏兵で十日初日のおくれた大阪歌舞伎座の新派大合同はまずまずの入り、ヒルの部は八木隆一郎作「命美わし」泉鏡花作「逢坂の辻」火野葦平作「女侠一代」の三本立でいずれも文芸作品である