|
(中座) 気魄滲む「夜叉王」 案外粗雑な又一郎の挙措 富田康彦
さて「鎌倉三代記」は久々の丸本歌舞伎、一代の名優父鴈治郎が京顔見世興行での最後の舞台をしのばす又一郎の三浦之助はその風貌を写して、この優以外にはないはずだが、その手負いの挙措は案外に粗雑だつた――たとえば最初にのれん口に入る条、井筒にかかるまでの足の運び「佐々木・・」と呼び出す間の意気組みも、練れてはない、柱を効果的に使わぬのも演技の上では損である、高綱は若い延二郎であるが、藤三郎の間も悪くなく後の出でも河内家型の踏襲で、まず無難という域だけのもの、これに重味の加わるは今後のこと、雛助の時姫は古典味のないのは止むを得ないとして、ひたすら姿態美を追わんとする意あまつて役柄の滋味に乏しい 岡本綺堂作「修善寺物語」は先代左団次が累世の当り芸であり、今もなお不朽の名品たり得たのは故人の力であるが、この狂言を同優歿後第一に取り上げたのは訥子であり、その夜叉王には左団次の型を一応咀嚼(そしやく)しつつ、今や完全に自家薬籠中のものにしてしまつている、この劇を最高潮に盛り上ぐる「姉は死ぬか、姉もさだめて本望であろう、父もまた本望じゃ・・」からのセリフの一つ一つにも名匠気質の気魄というものを一句々々にみなぎらしていた 次に仁左衛門の頼家も佳品である、この役は書卸しの先代羽左衛門をはじめ、梅幸、鴈治郎(いずれも先代)や故延若、吉右衛門などの名優が演じたものである、次に重い役は姉の娘桂である、書卸しに女形でなかつた寿美蔵(今の寿海)が抜てきされたほどの難役、気位の高くそして典雅な色気もどこかににじみ出ていなければならぬ役柄なので、はじめ妹娘楓をやった故松蔦が、ずつと適り役とされたものだ、今度の菊次郎もこれらの条件にはそつているが、さらに一段の洗練を望む、みんしの春彦は立派である、この俳優を女形のみでなくもつと重用して見たいと思う、もう一人奥山の僧は当然ながら認めて置く それから仁左衛門のこれもお家芸「大文字屋」があつたが、評者は病躯のため割愛した |
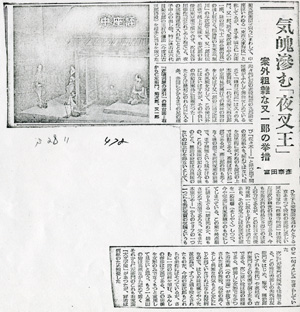 菊五郎劇団を向うにまわして、中座はいわゆる「東西大歌舞伎」と称しているが、まず手頃な仁左衛門、又一郎、訥子、菊次郎ら中心の一座、昼の部に「十二時会稽曽我」の通し狂言と、松島屋のお家芸「堀川」の与次郎で見せ、又一郎は伝兵衛で純上方風味を、菊次郎のお俊は東京型で顔を合せ、次は長谷川伸作「討たれてやらぬぞ」と、夜の部菊池寛作「入れ札」とともに訥子中心の出し物、特に後者は六代目菊五郎の玉村の弥助(今度は吉三郎持役)を相手に当りを取った先々代仁左の老役稲荷の九郎助を同優がふんして舞台をしめている
菊五郎劇団を向うにまわして、中座はいわゆる「東西大歌舞伎」と称しているが、まず手頃な仁左衛門、又一郎、訥子、菊次郎ら中心の一座、昼の部に「十二時会稽曽我」の通し狂言と、松島屋のお家芸「堀川」の与次郎で見せ、又一郎は伝兵衛で純上方風味を、菊次郎のお俊は東京型で顔を合せ、次は長谷川伸作「討たれてやらぬぞ」と、夜の部菊池寛作「入れ札」とともに訥子中心の出し物、特に後者は六代目菊五郎の玉村の弥助(今度は吉三郎持役)を相手に当りを取った先々代仁左の老役稲荷の九郎助を同優がふんして舞台をしめている