|
「本朝廿四孝」は武田、上杉両家の確執を背景に両家の忠臣横蔵(実は山本勘助)、慈悲蔵(実は直江山城守)の活躍(三段目まで)と、武田の一子勝頼、上杉の息女八重垣姫の恋(四段目以降)が軸になっており、背後で斎藤道三が暗躍するなど複雑な筋立てである。それだけにポピュラーな四段目「十種香・奥庭」のみの上演が多いが、今回は序段から三段目までを通す。ところがその三段目「勘助住家」がまことに難解である。 まず横蔵(勘助)と慈悲蔵(直江)を兄弟に仕立てその亡父も山本勘助であったり、母に盲従する慈悲蔵はわが子を捨て兄横蔵の子を養育、その子が実は将軍の若君であったり、すったもんだのあげく突如慈悲蔵が直江山城守に変身したり、裏のまた裏を設定する複雑さで、初めて見る者には不可解そのものであろう。だが一方中国の廿四孝、孟宗の雪中のたけのこ堀りの古事をとり入れるなど題名の由来となるところでもあり、仕どころも多く、文楽でも歌舞伎でも重きをなしている作品だ。それに勘三郎(慈悲蔵)、幸四郎(横蔵)の好演に加えてワキも雀右衛門(お種)、菊次郎(越路)、吉右衛門(景勝)、宗十郎(唐織)とそろい重厚な舞台をくり広げている。 前に発端の「足利館」と「お百度石」「桔梗ケ原」がつき、筋を通している。26日まで。 (写真)勘三郎の慈悲蔵(右)と幸四郎の横蔵 東横劇場・帝国劇場 東横劇場 前進座「哀より愛へ」は脱獄囚の丈八が事業に成功、恵まれない幼女を引きとって養育するかたわら貧しい人々に施しをしているが、いつも官憲につきまとわれる――というユーゴーの「レ・ミゼラブル」の翻案で時代を明治の白由民権期におきかえている。幼女の小さとは美しく成長し、竜介という青年となれそめ、竜介は秩父事件にまき込まれて負傷するが曲折ののち二人は結ばれる。原作は若い二人に祝福されながらジャンバルジャン(丈八)は死んでいくのだが、ここでは丈八も、丈八を追う警官もお遍路に変身して巡礼の旅に出る、というラストがシャレており、翫右衛門(丈八)、のり平(條野巡査)のこの場の演技に“ああ無情”の切実感がある。ほかに国太郎(三世国太郎)、嵐圭史(竜介)、小堀薫(小さと)、岩五郎(貞蔵)、村田吉次郎(春山)という配役。22日まで。 帝国劇場 長谷川一夫に尾上梅幸という珍しい顔合わせ。植田紳爾脚本の「歌麿」でこの二人の顔が合う。 二幕十七場の各場に邦楽と洋楽の伴奏をあしらったミュージカル風絵巻物で、いかにも長谷川好みの理屈ぬきの明るく楽しい作品になっている。これといったストーリーもないが、女の美しさを描いて人々に夢を与えるという歌麿の自負と、人に喜ばせるためではなくきたないものでも自分の描きたいものを描くという写楽の主張が根底にあり、それに蔦屋重三郎や写楽の友情、歌麿・おふくの夫婦愛をたくみに配合している。長谷川の歌麿、梅幸のおふくがイキを合わせ、歌麿がスランプを克服するラストが盛り上がる。又五郎の蔦屋が柔軟な演技で、ほかに春日野八千代、甲にしき、朝丘雪路、長谷川稀世とまわりがはなやかだ。 「砂の花」は若き日のジンギスカンの純愛物語だが、長谷川のジンギスカンはウエットにすぎて一般に想像される英雄のイメージにほど遠い。29日まで。 (岡田) (写真)長谷川の歌麿(右)と梅幸のおふく |
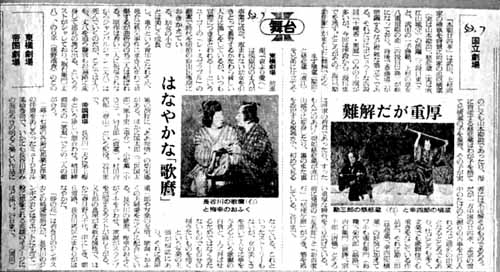 国立劇場
国立劇場