|
=尾= 上松緑はいま、荒事の演技にかけては第一人者であり、加えて父の七世松本幸四郎は、メーキャップの名人だった。東京・紀尾井町の自宅で、隈取りの話をたっぷり聞いたが、興に乗った彼は、役者の化粧の珍談もいくつか話してくれた。まず開口一番「私たちのメーキャップは隈にかぎらず、化粧しながらその役に入ってゆくことが大事です。またしっかりした演技の裏付けがないと、隈も引き立たない。お能で面(おもて)負けとい いますね。いい面はいい腕の人でないとかけさせない。歌舞伎のメーキャップもおんなじですよ」。 =隈= の種類は多い梅王の筋隈、和藤内の一本隈、のち日本隈、松王の日本隈、助六や五郎のむきみ隈、忠信のきつね隈、知盛の亡霊隈・・・。顔料は紅(あか)、藍(あい)、茶、タイシャ、灰色などで、紅は洋紅、青はセイタイ、茶は茶墨を使う。色によっておおまかに性格が分かれるのは、地塗りの色でも白は善人、赤が勇者とか敵役になるように、限取りも紅は正義、情熱、武勇、藍は冷血、かん悪、黒や茶は神霊、鬼畜、化生(けしょ う)と、ほぼ大別される。付け足りだが、いい加減な役は、隈もいい加減にしないと、かえっておかしくなる。「天下茶屋」のやくざな家臣の元右衛門など、初めはまじめな若党で、あとで三枚目の端敵になるような人物は、化粧ではかえって気を使う。 「京劇の人の隈も見たが、こちらはリアルで、孫悟空はサルらしく、武将はいかにも武将らしい。歌舞伎の方はだいぶ様式化してるが、それでも忠信のきつね隈など、マユ毛がしらに二本、鼻の下に一本引くだけで、ケモノらしい感じがじつによく出ます」 「兄の団十郎はあまり化粧にこらなかった。いい男は顔の土台がいいから、これでいいわけで。おやじの幸四郎も立派な顔をしてたが、こちらは化粧にこりすぎた。絵心もあったし、役者の顔はきれいだけじゃいけない。遠見が利かないとダメだと、日ごろ教えてま した」 「その父が立役の化粧は年をとらんとサマにならんと話していた。若いと皮膚がはりきってて、白粉を真っ白に塗るとハレーションを起こす。四ノ切の本物の忠信で、息子の辰之助にはセイタイをつけさせたが、私はやらなかった。もう年で、顔に陰影が出てますから」 =お= 父さんの化粧で面白い話をしてくれた。この人が「忠臣蔵」の定九郎を演じたとき、先祖の鼻高幸四郎(五世)のことが頭にあったのか、自分も鼻を高くした。もともと幸四郎の鼻は高かったから、松緑さんの観察ではわざわざそうしなくともいいのに、彼は苦心して、蝋(ろう)を使って鼻高に。ところが寒中で、昔の役者は冬は暖かいふろ場で化粧してたから、その湯気で「おやじの鼻が溶けちゃったんですよ」 それはともかく、隈というものは「暫」のせりふ通り、寒ボタン式に、たたいて、ボカすことが肝要とか。「むつかしいのは助六などのむきみ隈で、ひとつ間違うとべッカンコになっちゃう。この場合は隈取りして、江戸紫のハチ巻きをつけて、初めてしまる。いや、よく考えたものだと思いますよ」。どうやら隈取りには、その演者の付ける大時代な衣装やマゲとのつり合いも、考慮されているようだ。 (山口 龍之輔記者) |
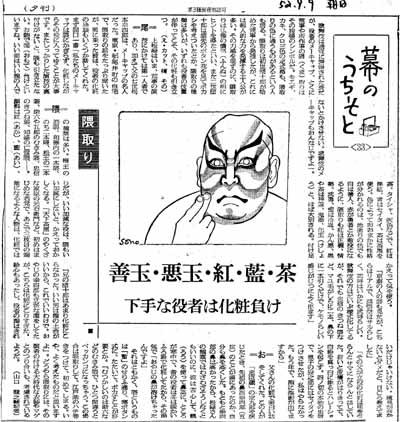 歌舞伎は適宜に誇張された芸だが、役者のメーキャップ、とくに荒事や所作事の隈(くま)取りはその誇張のシンボルだ。モエギ、カキ、クロ三色の定式幕も、隈取りの色に通うものがあるという人も居る。隈取りは初世団十郎が始めた荒事から発達したが、これには超人的な力を発揮する主人公が多い。その力感を現すのに、隈取りは仏像の憤怒(ふんぬ)の相にヒントを得たといい、また二世団十朗は庭先のボタン花を見てボカシを考えついたとか。隈取りの種類は多いが、いずれも役者の技量が伴ってこそ、その化粧も引き立つ。 (え・カット、榎 その)
歌舞伎は適宜に誇張された芸だが、役者のメーキャップ、とくに荒事や所作事の隈(くま)取りはその誇張のシンボルだ。モエギ、カキ、クロ三色の定式幕も、隈取りの色に通うものがあるという人も居る。隈取りは初世団十郎が始めた荒事から発達したが、これには超人的な力を発揮する主人公が多い。その力感を現すのに、隈取りは仏像の憤怒(ふんぬ)の相にヒントを得たといい、また二世団十朗は庭先のボタン花を見てボカシを考えついたとか。隈取りの種類は多いが、いずれも役者の技量が伴ってこそ、その化粧も引き立つ。 (え・カット、榎 その)