|
=ど= この劇場でも次の月の狂言が決定し、配役も決まると、カツラ屋さんには「かっら付け帳」というのが回って来る。それには「この役者にはこの頭で行く」と書いてあるから、その注文に従って仕事を始める。だいたい古典物は決まりのカツラがあるが、立役、女形とも幹部級の役者にはカツラ師と床山さんが立ち合い、相手の希望を聞く。鈴木さんは「この役者のイキ(注文)が、いつも全部ちがうんですよ」と話してくれた。 カツラの土台である台金は、アカガネで作る。もっともこの方は役者の頭に合わせたら、一生カツラ屋で保管する。髪の方は一カ月芝居で使うと、汗のためにダメになる。しかし役者が太ったり、やせたりして、その土台を訂(なお)すことがある。第一肥えて来るとエリ(首筋)が変わる。また普通の人でも、オデコが張つた人はたいてい後ろが落ち込んでいる。いびつな頭の人も多いが、そこらをうまく見せるのがカツラ師の腕である。 そこで楽屋へ行って、役者の鏡台の前でカツラ合わせをするのだが、これを面倒くさがる役者も居る。しかし肝心のクリ(生え際)など、これをしないとサマにならない。鈴木さんの観察では、いまの若い役者は頭も大きく、おまけに長髪だから、カサばって来て、どうにも形が悪い。その点、中村歌右衛門などは日ごろきれいに整髪して、カツラの映りがいい。やはり日本一の女形の心掛けであろう。 =台= 金には、ビン、タボ、月代の部分に毛髪を植えた羽二重や、ミノ編みにした髪をとりつけて、床山に渡す。テレビ、映画の時代物では、キッコウと呼ぶナイロンの網に毛を植えたものを使うこともあるが、歌舞伎ではふつう羽二重。その毛の植え方だが、クリぎわ、つまり生え際から約二センチまでは一本一本植えつけ、その奥も二、三本ずつ植える。こうしないと毛の量がふえない。奥を濃く、生え際を薄くする。そのやり方は特殊なノリではりつけたり、ミノ編みの手法を用いたり。鈴木さんはどんな髪型でも、八時間で羽二重に毛を通す。やはり注文の細かい人は歌右衛門や玉三郎らの女形が多いそうだ。 その植えつける頭髪は、近ごろは中国やベトナムから、長短束ねて送られて来る。カラスの濡(ぬ)れ羽色などと賞(め)でた日本人の光沢のある髪も、現在は短髪が多く、いまや使えない。黒、白の毛では、ことに白髪の長いものが不足がちとか。そこで白毛にも、ナイロンを染めて使ったりする。が、シャグマという、たとえば「連獅子(れんじし)」で親子獅子が頭につける長い赤、白の髪は、昔からヤクの毛を使う。「助六」の敵役のヒゲの意休のヒゲもヤクの毛、「茨木」の老女もシャグマとナイロンをミックスしたものを使う。 =こ= うして出来たお姫様の吹輪とか、芸者のつぶし島田、やくざのむしり、二枚目の二つ折りなどいろんなカツラはカツラ師で仕立てて、床山に渡す時はざんばら髪にして渡す。それに髪の仕掛けは床山の担当だ。立ち回りで、役者のマゲの根元がくずれるガッタリなどの仕掛けもこちらでする。が、鈴木さんの話では「四谷怪談」のお岩の髪すきの仕掛けは、カツラ師が受け持つのだそうだ。幕内のしきたりには、ややこしいものが多い。(山口 龍之輔記者) |
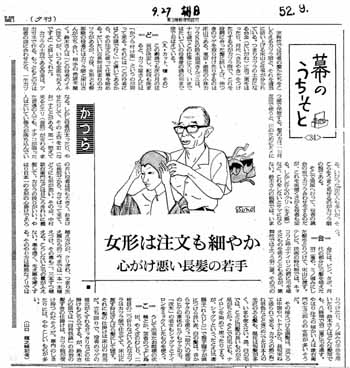 歌舞伎では役者の髪かたちをこしらえるカツラ師と、それを適当に結い上げる床山と仕事が分かれている。つまりカツラの土台になる台金(だいがね)に羽二重をはったり、月代(さかやき)をつけたりするのがカツラ師で、これを役柄に合った髪に結い上げ、油つきのマゲを取り付けたりするのは床山である。東京・銀座の小林カツラ
歌舞伎では役者の髪かたちをこしらえるカツラ師と、それを適当に結い上げる床山と仕事が分かれている。つまりカツラの土台になる台金(だいがね)に羽二重をはったり、月代(さかやき)をつけたりするのがカツラ師で、これを役柄に合った髪に結い上げ、油つきのマゲを取り付けたりするのは床山である。東京・銀座の小林カツラ