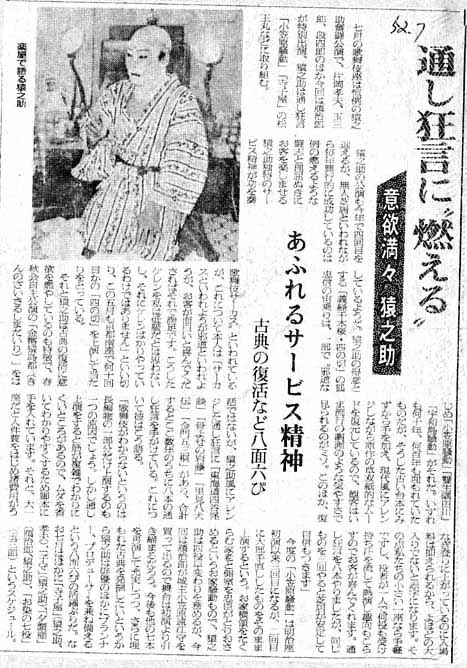|
猿之助の公演も今年で四回目を迎えるが、無人芝居といわれながら毎年興行的に成功しているのは例の燃えるような闘志と理屈ぬきにお客を楽しませる猿之助独特のサービス精神が功を奏しているようだ。猿之助の得意とする「義経千本桜・四の切」の狐忠信の宙乗りは、一部で〝邪道な歌舞伎サーカス〟といわれているが、これについて本人は「サーカ スといわれようが邪道といわれようが、お客が面目いと喜んでくださればそれで満足です。こうしたケレンを私は低級だとは思わないし、それにケレンばかりやっているわけではありません」といい切り、この五月も京都南座で何十回目かの「四の切」を上演して当たりをとっている。 それと猿之助は古典の復活に意欲を燃やしているのも特徴で、春秋会自主公演の「金幣猿島都(きんのざいさるしまだいり)」をはじめ「小笠原騒動」「雙生隅田川」「宇和島騒動」がそれだ。いずれも何十年、何百年も埋もれていたものだが、そうした古い台本にみずから手を加え、現代風にアレンジしながら原作の草双紙的なムードを復元しているので、観客はいま流行の劇画のような気やすさで見られるのがミソ。このほか、復活ではないが、猿之助風にアレンジした通し狂言に「東海道四谷怪談」「骨よせの岩藤」「里見八犬伝」「金門五三桐」があり、合計するとここ数年のうちに八本の通し狂言を手がけている。これについて彼はこう語る。 「歌舞伎がわからないというのは長編物の一部分だけ上演するのも一つの原因でしょう。しかし通し上演をすると筋が複雑でわかりにくいところがあるので、ムダを省いてわかりやすくするため脚本に手を入れています。それと、大一座だと人件費をはじめ諸費用がうなぎ登りに上がっているのに入場料は抑えられるから、よほどの大入りでないと赤字になります。その点私たちの小さい一座なら手軽ですし、役者が一人で何役も受け持ち汗を流して熱演し趣向もこらすのでお客が喜んでくれます。通し狂言を八本やりましたが、同じ ものを三回やると芝居が安定して自信もつきます」 今度の「小笠原騒動」は明治座初演以来三回目になるが、二回目に大部手直ししたものをそのまま上演するという。お家横領をたくらむ家老と側室を忠臣がとりおさめるというお家騒動もので、猿之助は四役早変わりを務めるが、今回は鴈治郎が城主小笠原遠江守を 買って出るので舞台は初演より引き締まるだろう。今後も他の七本を再演して充実しつつ、さらに埋もれた古典を発掘したいというから猿之助は俳優のほかにプランナー、プロデューサーを兼ね備えるという八面六ぴの活躍ぶりだ。なお七月はほかに「寺子屋」(猿之助、孝夫)、「子守」(猿之助)、「夕顔棚」(鴈治郎、猿之助)、「お染の七役」(玉三郎)というスケジュール。 (写真)楽屋で語る猿之助 |