|
本名・ ≫明治の〝ロック〟 「昔は六つの時から芸事を習うたんですな。家は染物屋でしたが親が浄瑠璃が好きで。十五、六の時に上の学校のこともあって親がやめろと言うころには、好きになってやめられへんようになってしもうて」 娘義太夫というのは女の義太夫語り。とくに若い女性が日本髪に花かんざしを飾り、はでな衣装で見台に伸び上がって語るので人気があった。全盛期は明治の半ば。定席には書生(学生)たちが毎晩のように通い、手拍子を取って「ドースル、ドースル」と声を掛け、熱狂した。ロック・コンサートのような騒ぎだったのだろうか。しかしオカミの意向で学生の出入りが禁止されて次第に衰え、関東大震災を境に、定席はほとんど壊滅した。(演劇博物館編「芸能辞典」) ただし、それだけのものが一度になくなるわけがなく、昭和の初めにはまだ方々になごりが残っていて、衰微の半面、それまでの華やかなショー的要素が落剥(はく)して、より純粋な〝芸″の本道に近づいていったといえる。 ≫座り込み入門 昭和五年、女師匠、豊沢小住(こすみ)に入門、団秀(だんひで)の名でプロに。二十四歳、小住の仲人で結婚。相手は東大阪の資産家。……ここまでは順調だが、この先が並みの人間と異なるところ。 「戦争の間はじっとしてましたけどね。戦争が終わったら、さあ、どうしても三味線がやりたい。あちらさん(ご主人)は〝趣味でやれ〟いわはる。わたし、二つと生まれたばかりの男と女の子連れて、家を出ました」 子供が成人するまで養育費を送れと談判して飛び出したというから大したもの。そのころ大阪に住んでいた実家の母に二人の子を預け、再び三味線の道に。もっとも「それで小住お師匠はんをクビになって」寛治師の門をたたいた。 「女の弟子はいやや、と言わはるお師匠はんの家に、一日くらい座り込んで、そのころ生きてはった文五郎(吉田)はんの口添えでようやく入門」。昭和二十六年、寛八の名をもらった。今になったら、あんな思い切ったこと、よう出来たなと、こわくなってくると言う。 ≫「アホ」に耐える 「そら厳しいお師匠はんでした。男も女も差別おまへん。毎日、アホ、バカの連続。扇子でたたかれっぱなし。毎朝、お宅へ行きますけどケイ古してくれはるかどうか分からへん。どこへ行かはるにもついて行きました。四つ橋の文楽に出てはる時は楽屋の世話。五十年の夏に八十八歳で死なはるまで、最後の最後までつきっきりでした」――そのころ四十キロだった体重が、寛治の死後急に太り出して、いまは六十三キロになったと笑う。 大阪港に近い しかし話していると、なにか透徹した、さわやかな心の動き――とでもいうものが、どんどんこちらに伝わってくる。生涯を一芸にうち込んだ人たちに共通する何か――。 ≫三人だけ弟子 今は子供たちも一人前になり、あんまり弟子がたくさんだと、自分の勉強する時間がなくなるから、弟子は三人だけにして、年に二回の大阪公演、東京の寄席出演などを中心に三味線ざんまい。舞踊会の演奏で、結構女ひとりの暮らしは立つ。 しかし、寛八のあとに続く者がいない。人形浄瑠璃に携わる人々で組織している「人形浄瑠璃因(ちなみ)協会」には女子部の太夫が四十数人、三味線が三十人いる。しかし街のお師匠さんがほとんどで、舞台でやる人は太夫、三味線合わせて十数人。しかも多くが八十歳、七十歳の高齢だ。いずれ消滅せざるをえないだろう――この時ばかりは、寂しそうな顔をした。 「なんでこないに三味線が好きか。結局、難しいからやないかしら。どこまで行っても奥が分からへん。もう一度、今度こそは……の繰り返し。そやから八十になってもやめられない。どっかほかの芸と違うものがあるのですやろか」 写真のために演奏してもらった。なぜか〝お里・沢市〟の「壷坂」。寸ごうもためらいのない確かな太棹(ざお)の音がほとばしって、ガラス障子がビリビリとふるえた。 (写真)太棹の音がビリビリとガラス障子を打つ鶴沢寛八さんの三味線 |
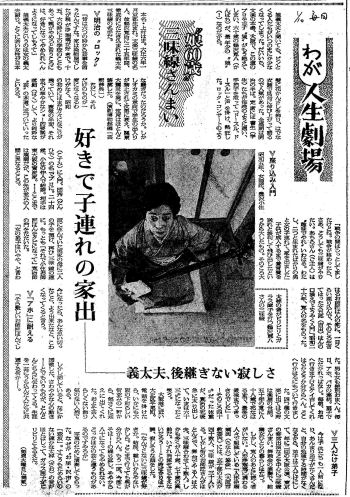 娘義太夫と聞いても、ピンとくる人たちがいつのまにか少なくなってしまった。だいいち、文楽の本場、大阪で、この道のプロを志す〝娘″がもう絶えてしまい、六十歳の鶴沢寛八(かんぱち)が、最年少の〝娘〟(!)なのだから。
娘義太夫と聞いても、ピンとくる人たちがいつのまにか少なくなってしまった。だいいち、文楽の本場、大阪で、この道のプロを志す〝娘″がもう絶えてしまい、六十歳の鶴沢寛八(かんぱち)が、最年少の〝娘〟(!)なのだから。