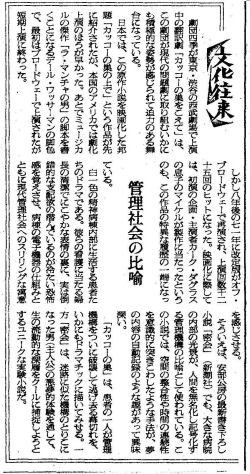|
日本では、この原作小説を映画化した邦題「カツコーの巣の上で」という作品が先に紹介されたが、本国のアメリカでは劇化上演のほうが早かった。あとでミュージカルの傑作「ラ・マンチャの男」の脚本を書くことになるデール・ワッサーマンの脚色で、最初はブロードウェーで上演されたが短期上演に終わった。 しかし八年ごの七一年に改訂版がオフ・ブロードウェーで再演され、上演回数千二十五回のヒットになった。映画化に際しては、初演の企画・主演者カーク・ダグラスの息子のマイケルが製作に当たったというのも、この作品の特異な履歴の一端になっている。 白一色の精神病棟内部に生活する患者たちのドラマである。彼らの看護に当たる婦長の清潔でにこやかな表情の裏に、実は倒錯的な支配欲の潜んでいるのが冷たい恐怖感を覚えさせ、病棟の電子機器の仕組みとともに現代管理社会へのスリリングな寓意を感じさせる。 そういえば、安部公房の最新書き下ろし小説「密会」(新潮社)でも、大きな病院の内部の光景が、人間を無名化し記号化する管理機構の比喩として使われている。この小説では、空間の整合性や時間の連続性を意識的に突きこわしたような手法が、夢の内容の自動記録のような趣があって興味深い。 「カツコーの巣」は、患者の一人が管理機構をついに破壊して逃げ去る幕切れを、いかにもドラマチックに描いてみせる。一方「密会」は、迷路に似た機構のとりこになった男(主人公)の悪夢的体験を通して、生の流動的な深層をクールに捕捉しようとするユニークな実験小説だ。 |